久留米市は人口約30万人の中核都市で、高齢化率は2020年時点でおよそ28〜29%、市の計画では2025年前後に30%前後に達すると見込まれています。(GDFreak)
高齢者人口が増えるほど、介護サービスの利用も増え、老人ホームやデイサービス、訪問介護の現場では、利用者・家族・職員の関わりが密になります。
その中で、
- きつい言い方が続いて職員が泣きながら休憩室に戻る
- 認知症の利用者からのセクハラが習慣化してしまう
- 家族からの電話クレームが一人の職員に集中する
といった場面は、久留米市御井旗崎の「有料老人ホームはたさき」のような中規模施設でも起こり得ます。
この記事は、
- 利用者家族
- 老人ホーム・通所系サービス・訪問介護で働く職員
- 事業所の管理者・経営者
が、同じ目線でハラスメントを考えられるように書いています。
久留米の介護現場でハラスメントが起きやすくなる背景
久留米市の介護現場では、ちょっとした行き違いがきっかけとなり、職員が「責められている」と感じる場面が増えています。最初は細かな不満でも、説明や対話の機会が足りないまま時間が経つと、声のトーンや言葉の選び方がきつくなり、ハラスメントに近い状態へ進みます。
高齢化率30%前後の地域で起きやすいすれ違い
久留米市は、高齢化率がおよそ30%に届く水準まで上がっている地域です。(earthsupport.net)
介護保険サービスの利用者も増え、同じ老人ホームに複数の家族が関わり、ケアマネジャーや訪問看護など関係者も多くなります。
人が増えると、それぞれの「当たり前」がぶつかります。
- 家族の「これくらいやってもらえるはずだ」という感覚
- 職員の「介護保険のルールに沿って動きたい」という感覚
- 事業所の「限られた人数で全員を支えたい」という感覚
この3つが揃うと、一方の善意が別の人にとっては負担になることがあります。
例えば、家族は「散歩ぐらい毎日連れて行ってほしい」と願っても、職員は他の入居者の排泄介助や記録業務で手一杯という日もあります。
このすれ違いを放置すると、「お願いが届かない」「文句ばかり言われる」と互いに感じ始め、言葉が荒くなりやすくなります。
御井旗崎エリアに多い「比べられる」プレッシャー
久留米市御井旗崎周辺は、介護事業所が集まるエリアです。
有料老人ホームはたさきのような施設に入居している家族は、別の老人ホームや通所介護の話も耳にします。
- 「別の施設ではここまでやってくれた」
- 「あそこのデイサービスはレクリエーションが多いと聞いた」
こうした比較が続くと、現在の施設への期待値が少しずつ上がっていきます。
説明が追いつかないと、「やってくれない」「手を抜いている」と受け止められ、職員への言葉が厳しくなります。
現場としては、
- 自分たちができる範囲
- 他サービスと組み合わせて対応した方が良い部分
を、早い段階で共有しておくことが欠かせません。
人手不足と感情コントロールの難しさ
久留米市に限らず、介護業界全体で人手不足が続いています。(久留米市公式サイト)
1人の職員が、食事介助・排泄介助・記録・ご家族対応を同じ時間帯に抱えるシフトも珍しくありません。
余裕がない状態では、
- いつもよりきつい口調になる
- 表情がこわばる
- 細かな配慮に気づきにくくなる
といった変化が出ます。家族から見ると「冷たく感じる」「雑に扱われた」と受け止められやすくなり、苦情や怒りの言葉につながります。
この連鎖を断つには、個人の「気合い」ではなく、シフトや役割分担を見直し、感情が荒れそうな場面を減らす工夫が必要です。
老人ホームで実際に起きているハラスメントのパターン
ハラスメントと言っても、内容は一つではありません。久留米の老人ホームやデイサービスで出やすいパターンを整理しておくと、自分の現場がどこに当てはまるか見えやすくなります。
利用者・家族から職員へのカスタマーハラスメント
老人ホームでは、利用者だけでなく家族からの強い言動も目立ちます。たとえば次のような場面です。
- 契約外の掃除や洗濯を何度も頼み、「それぐらいできないのか」と責める
- 介助の順番が前回と違っただけで、「うちの親を後回しにしたのか」と大声で怒る
- 連日同じ内容の電話を長時間続け、特定の職員を名指しで批判する
こうした行為が続くと、職員は「この家族に当たる時間帯だけ緊張で胃が痛い」といった状態になりやすくなります。
同時に、他の利用者への対応が遅れ、全体のサービスにも影響が出ます。
よくある場面と望ましい対応の例
| ハラスメントの内容 | ありがちな対応 | 望ましい対応の方向性 |
|---|---|---|
| 契約外の家事を強い口調で繰り返し要求される | 職員がその場しのぎで受けてしまう | 契約書とサービス表を示し、管理者と一緒に説明する |
| 長時間の電話クレームで特定職員が拘束される | 同じ職員が毎回対応し、疲弊していく | 対応者を固定せず、記録を残しながら責任者に引き継ぐ |
| 人前で人格を否定する言葉を投げかけられる | 職員が笑ってごまかし、その場をやり過ごす | その場を離れる権限を認め、後日管理者から正式に説明 |
「顧客だから我慢する」という考え方だけで対応すると、職員の心身が先に限界を迎えます。
あらかじめ「どのレベルから管理者が出るか」「相談窓口へつなぐか」を決めておくと、早めにブレーキをかけられます。
セクシュアルハラスメントと身体接触の問題
介護の仕事は、身体に触れる場面が日常的に続きます。そこに認知症や精神面の不安が重なると、セクハラに近い言動が出やすくなります。
例えば、
- 入浴介助のたびに、職員の胸や腰を触る
- 「若い子が来ると元気が出る」と体型や年齢をしつこく話題にする
- 夜勤のたびに「部屋に来て」「一緒に寝てほしい」と呼び出す
といった行動です。
職員側が「利用者だから」「認知症だから」と自分を納得させてしまうと、訴えるタイミングを失い、そのうち心身の症状として現れます。
現場で取れる一歩として、
- 一人で密室になりやすい場面は二人介助に切り替える
- 問題が続く利用者については、ケアプランに「声かけの方針」や「介助方法」を書き込む
- 家族にも状況を伝え、医師やケアマネジャーを交えて話し合う
といった方法があります。
職員同士で起きるパワハラ・モラハラ
老人ホームの中では、職員同士の関係が壊れていくケースも少なくありません。
忙しさや人手不足から、指導の言葉が次のような状態に変わっていくことがあります。
- ミスを何度も人前で責める
- 「向いていない」「前の職場に戻った方が良い」と人格に踏み込む
- 特定の職員だけ情報共有から外す
この空気に慣れてしまうと、新人が定着せず、残った職員も「ここでは強くないと生き残れない」と感じるようになります。
パワハラを減らすには、
- 指導は個別面談で行い、内容を事前にメモしてから話す
- 行動と事実に焦点を当て、「あなたはダメ」ではなく「この場面ではこうしてほしい」と伝える
- 年に一度は外部講師による研修を入れて、現場で線引きを共有する
といった地道な見直しが欠かせません。
施設として整えておきたい仕組みとルール
ハラスメントは、個人の我慢で何とかする問題ではありません。老人ホームや訪問介護事業所として、「ここまでは対応する」「ここからは線を引く」という仕組みを用意することで、職員も家族も迷いにくくなります。
就業規則と契約書に「線引き」を書き込む
まず整えたいのは、紙に残るルールです。
- 就業規則に、セクハラ・パワハラ・カスハラの定義と例を記載する
- 利用契約書や重要事項説明書に、「暴言・暴力・過度な要求に対する施設の方針」を入れる
- 「洗濯」「掃除」「買い物」など家事サービスの可否を一覧にして家族へ渡す
有料老人ホームはたさきのように、パンフレットや入居説明の資料に一覧表を入れておけば、現場職員が断る際にも「施設全体のルール」として説明しやすくなります。
ルールを書き込んだ後は、年に一度は職員全員で読み合わせを行い、「この表現だと現場に合わない」などの意見も集めて更新していくと運用しやすくなります。
研修とロールプレイで「言い方」を準備しておく
用紙や規程だけでは、現場の一瞬の判断を支えきれません。
そこで、研修やロールプレイで「その場で口から出る言葉」を準備しておきます。
例として、年2回の研修で次のテーマを扱います。
- 契約外の依頼を断るときの伝え方
- セクハラ発言を受けたときの場の離れ方
- 電話クレームを短時間で区切る方法
ロールプレイでは、職員が「家族役」と「職員役」に分かれて会話を試します。
終わった後に、「この表現なら家族も受け止めやすい」「この言い方だと反発されやすい」と感想を出し合うと、現場で使える言葉が少しずつ揃っていきます。
記録・相談窓口・メンタルケアをひとつの流れにする
ハラスメントが続いても、記録や相談の仕組みがないと、管理者まで情報が上がりません。
次の3点を一つのセットとして動かします。
- 記録
- 「いつ・どこで・誰から・どんな言動があったか」を残す簡単な用紙をつくる
- クラウド型の介護記録システムを使っている場合は、ハラスメント用の項目を追加する
- 相談窓口
- 管理者だけでなく、看護師・主任・外部カウンセラーなど複数の相談先を用意する
- 匿名相談も受け付ける運用にして、声を上げやすくする
- メンタルケア
- 一定件数の相談が続いた職員には、短い面談やシフト調整を行う
- 必要に応じて医療機関の受診を勧め、診断が出た場合は勤務内容を一緒に見直す
この流れを毎月短く振り返るだけでも、「どの時間帯」「どの利用者」「どの種類の言葉」で職員が傷ついているかが見えやすくなります。
利用者家族がハラスメントを避けるためにできる工夫
ハラスメントの話になると、「加害者」として家族だけが取り上げられることがあります。
ただ、現場を見ていると、家族自身も介護疲れや不安で追い詰められている場合が多く、その気持ちの行き場が職員に向かっているケースが少なくありません。
最初に「頼めること・頼めないこと」を確認しておく
家族の不満の多くは、「ここまではやってもらえると思っていた」という期待とのギャップから生まれます。
入居やサービス開始のタイミングで、
- 食事・入浴・排泄・更衣・口腔ケア
- 外出付き添い・買い物代行・通院付き添い
など、具体的な項目ごとに質問を用意して聞いておくと、その後のズレを減らせます。
例えば、
- 「夜間のトイレ介助は、どの時間帯に何回くらいを想定していますか」
- 「外出の付き添いは、月に何回までお願いできますか」
といった聞き方にすると、施設側も説明しやすくなります。
不満や不安を伝えるときの「言い方」を変える
家族が疲れていると、どうしても言葉がきつくなります。
その場ではすっきりしても、あとで冷静になると「言い過ぎたかな」とモヤモヤが残り、職員との関係もぎこちなくなります。
伝えるときは、次の3点を意識すると、感情をぶつけずに済みます。
- 何が起きたか(事実)
- どう感じたか(気持ち)
- どうしてほしいか(希望)
例えば、
昨日の夜、父のパジャマが裏返しのままになっていました(事実)。
少し慌てて着替えさせたのかなと気になりました(気持ち)。
次から一度だけチェックしてもらえると助かります(希望)。
という形です。
一人で抱え込まず、第三者の窓口を使う
施設に直接伝えにくいときは、久留米市の地域包括支援センターなど、第三者の窓口を使う方法があります。(久留米市公式サイト)
- 「このお願いはやり過ぎかもしれない」
- 「施設に話すと角が立ちそうで迷っている」
といったとき、包括支援センターの職員に相談すると、介護保険の仕組みも踏まえて整理してもらえます。
必要なら、施設との話し合いに同席してもらうこともできます。
家族が一人で抱え込まずに話せる場を持つことが、結果的に職員を守ることにもつながります。
久留米の介護事業所が外部専門家と連携する際のポイント
最後に、久留米の老人ホームや訪問介護事業所が、法的支援や外部専門家をどう使えば、職員を守りながら事業を続けやすくなるかを整理します。
顧問弁護士・社労士・公的機関の役割を分けて考える
ハラスメントの中には、施設だけで判断するとリスクが読みにくいものもあります。
あらかじめ専門家とつながっておくと、次のような場面で助かります。
- 顧問弁護士
- 悪質なカスハラへの警告文作成
- 利用契約解除や警察相談を検討するときの助言
- ハラスメント防止規程のチェック
- 社会保険労務士
- 就業規則や懲戒規程の整備
- 職員からの相談が増えたときの労務面の対応
- 公的機関(福岡労働局の総合労働相談コーナー、法テラスなど)
- 初回相談での情報収集
- 労働紛争の解決手続きの流れの確認
久留米市の事業所であれば、年に1回は顧問弁護士と面談し、具体的な事例を共有しながら「ここから先は弁護士が前に出るライン」を決めておくと判断しやすくなります。
トラブル発生時のフローをシンプルに決めておく
現場が迷わないように、トラブルが起きたときの流れを紙1枚で見えるようにしておきます。
例:
- 職員が、「これはおかしい」と感じた言動をメモに残す
- その日のうち、または翌日までに上司か相談窓口に報告する
- 管理者が状況を聞き取り、記録を整理する
- 必要に応じて、家族面談・ケアプランの見直し・顧問弁護士への相談などに進める
- 対応の結果と再発防止のポイントを、職員会議で共有する
この流れが決まっていれば、夜勤の職員も迷わず動けます。
1年間で何を進めるかざっくり決めておく
いきなりすべてを整えようとすると、現場が追いつきません。
久留米市内の中規模老人ホームを想定すると、次のようなペース配分が現実的です。
- 1〜3か月
- 過去1年のトラブルを振り返り、種類と件数を一覧にする
- 就業規則・契約書の文言を読み直し、修正点をメモする
- 4〜6か月
- ハラスメント研修を1回実施し、代表的な事例を共有する
- ロールプレイで「断り方」「場の離れ方」を練習する
- 7〜9か月
- 新規入居者向け説明資料に、ハラスメント方針と相談窓口の案内を追加する
- 既存の家族にも、通信や面談で方針を伝える
- 10〜12か月
- 1年間の記録を集計し、件数や中身の変化を確認する
- 職員アンケートで「相談しやすさ」「安心感」を数値で把握する
このサイクルを毎年回すことで、現場に合う形へ少しずつ近づけていけます。
参考資料・出典例
記事の作成にあたり、久留米市や福岡県の公開資料を参考にしました。ブログに掲載する際は、必要に応じてリンクを貼っておくと信頼性が上がります。
- 久留米市「第7期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」(久留米市公式サイト)
- 久留米市 高齢者支援パンフレット(令和4年度版)(久留米市公式サイト)
- JMAP「福岡県 久留米市 高齢化率(2020年)」(JMAP)
- GD Freak!「久留米市の高齢化率の推移」(GDFreak)
- アースサポート株式会社 Web記事「久留米市の認知症問題を徹底検証」(earthsupport.net)



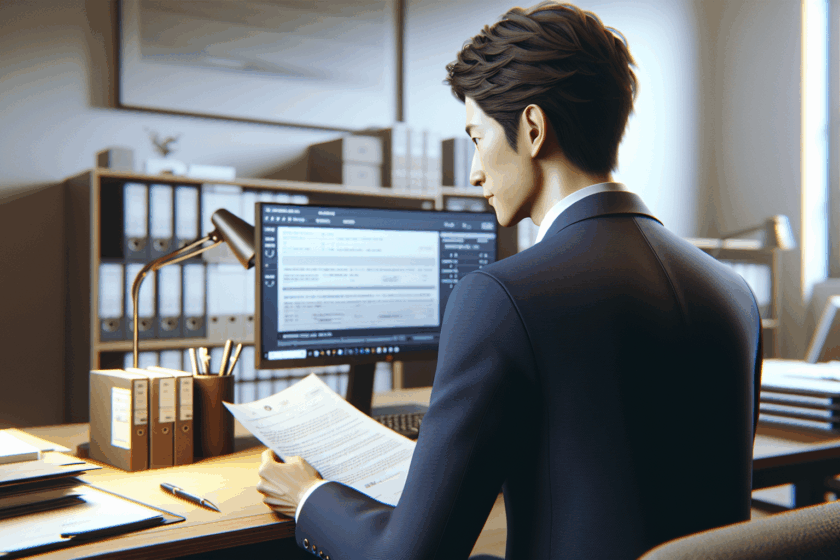





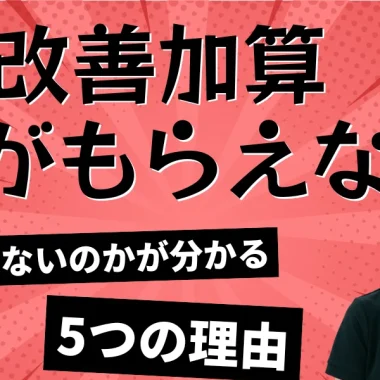








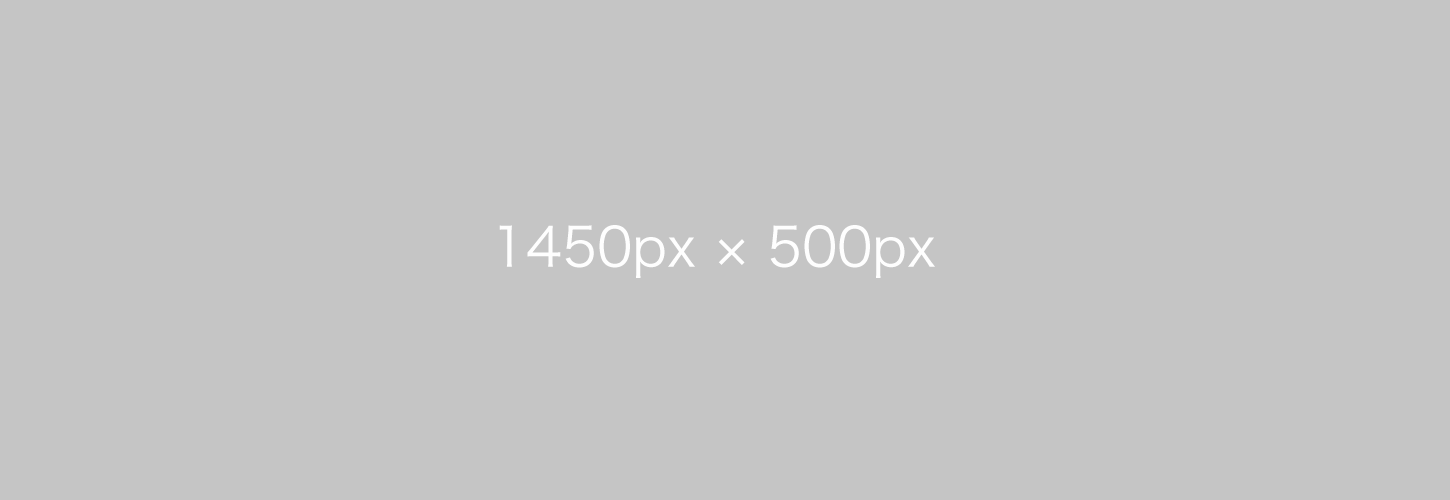
コメント