「久留米市に旅行に行きたいけど、どこを観光すればいいのかな…」「限られた時間で効率よく観光地を回りたいけど大丈夫かな…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
福岡県南部に位置する久留米市は、豊かな自然と歴史的建造物、そして美味しいグルメが楽しめる魅力的な観光地です。
初めて訪れる方でも、この記事を読めば必ず行きたい場所が見つかるはずでしょう。
この記事では、久留米市への旅行を計画している方に向けて、
– 久留米市の定番観光スポットとその魅力
– 効率的な観光ルートと所要時間の目安
– 各スポットの見どころと楽しみ方のポイント
上記について、解説しています。
久留米市には、歴史ある寺社仏閣から美しい自然スポット、家族で楽しめるレジャー施設まで、幅広い観光地が点在しています。
実際に訪れた人の評価や口コミを基にランキング形式でまとめましたので、旅行プランを立てる際の参考資料として活用できるでしょう。
久留米観光を最大限に楽しむためのヒントが詰まっていますので、ぜひ参考にしてください。
久留米市の地理と気候を知る
久留米市は福岡県南部に位置し、筑後平野の中心都市として発展してきました。
市域の大部分は平坦な地形で、東西に流れる筑後川が市の中央部を貫いています。
人口密度は1,3198人/平方キロメートルとなっており、九州北部における重要な中核都市の一つとして機能しています。
標高は概ね10メートルから20メートル程度で、農業に適した肥沃な土地が広がっているのが特徴です。
福岡県最大の農業都市「久留米」。
九州一の大河「筑後川」の恵みを受けた肥沃な筑後平野で生産された自慢の農産物が豊富に収穫されています。
特に久留米市は県内一のお米の生産地として知られ、久留米市田主丸町は巨峰の産地として知られています。
さらに久留米市三潴町は福岡県内では唯一のハトムギの生産地でもあり、農業の多様性が際立っています。
久留米市の気候は温暖湿潤気候に属し、年間を通じて比較的過ごしやすい環境にあります。
年間平均気温は約16度で、夏は蒸し暑く、冬は比較的温暖という九州地方特有の気候パターンを示しています。
梅雨時期の6月から7月にかけては降水量が多く、台風シーズンには注意が必要でしょう。
久留米市は福岡市から南東へ約40キロメートルの距離にあり、交通の要衝として重要な役割を果たしています。
北は小郡市と筑紫野市、東は大刀洗町とうきは市、南は八女市と広川町、西は大川市と佐賀県鳥栖市に隣接しており、筑後地方の中核都市として周辺地域との連携を深めています。
久留米市の産業面では、伝統工芸品が特に有名です。
久留米絣・八女福島仏壇仏具・八女提灯・籃胎漆器・城島鬼瓦・久留米おきあげ・筑後和傘・八女手漉和紙など、多彩な工芸品が製作されています。
また、久留米市は、日本三大植木産地のひとつで、特に三潴地区では庭園・観賞用の黒松の生産が盛んです。
この黒松は、百数十年の歴史と伝統があり「みづまの黒松」の名で全国的に有名となっています。
食文化の面では、とんこつラーメンは濃厚でクリーミーなスープと細麺の絶妙な組み合わせが特徴で、多くの店舗が独自の味を競い合っています。
また、焼き鳥は人口当たりの店舗数が日本一と言われ、特に「ダルム」と呼ばれる豚の腸を使った独特の焼き鳥が名物として親しまれています。
筑後うどんや久留米焼きめし、うなぎのせいろ蒸しなど、多様な郷土料理が地域の食文化を形成しています。
観光面においては、高良山に鎮座する由緒ある神社。
筑後国一の宮として知られ、式内社(名神大社)に列せられる1600年以上の歴史を持つ重要な社です。
本殿、幣殿、拝殿は江戸初期の権現造。
神社建築としては九州最大規模を誇り、国の重要文化財に指定されています。
高良大社は久留米市を代表する歴史的建造物として、多くの参拝者を集めています。
文化施設としては、久留米市出身で、世界最大のタイヤメーカー「ブリヂストン」の創業者・石橋正二郎が故郷に寄贈した美術館です。
地元出身の日本近代洋画家の多くの作品を所蔵しています。
現在は久留米市美術館として運営され、地域の芸術文化の発信拠点となっています。
自然を楽しめる場所として、久留米市の市政生誕100周年を記念して、平成元年に完成した公園で、毎年春には、市の花である「久留米ツツジ」12万本が咲き誇ります。
久留米百年公園は市民の憩いの場として親しまれています。
酒造業も盛んで、筑後平野の豊かな実りと、九州一の大河・筑後川が生み出す豊かな水。
これら恵まれた自然環境に杜氏の確かな腕が加わって、三潴地区では古くから酒造りが行われてきました。
現在、三潴地区では4軒の酒蔵があり、長い歴史と伝統を受け継いだ酒造りが行われています。
豊かな自然に恵まれた耳納連山(みのうれんざん)の麓や筑後川流域を中心に、15もの酒蔵が点在する名醸地としても有名となっており、地域の重要な産業の一つとなっています。
このように久留米市は、豊かな自然環境と肥沃な大地に恵まれ、農業・工業・商業がバランスよく発展してきた都市です。
伝統工芸品から最先端の産業まで、多様な産業が共存し、独自の食文化や歴史的建造物が地域の魅力を形成しています。
筑後地方の中核都市として、今後も周辺地域との連携を深めながら、さらなる発展が期待される都市といえるでしょう。
久留米市の地形と特徴
久留米市は福岡県南西部に位置し、筑後平野の中心都市として発展してきました。
市域は東西約32km、南北約16kmとなり、東西に長い自治体となっています。
市域の大部分は平坦な地形で、東西約155km、南北約118kmに広がっています。
北部には耳納山地が連なり、標高802mの鷹取山を最高峰とする山々が市街地を見守るように佇んでいます。
市の南部から南東部は耳納(みのう)連山と呼ばれる山地となっており、鷹取山・発心山・耳納山などの山々が連なっているのが特徴的な地形となっています。
市の中央部を筑後川が東から西へと悠々と流れ、その豊かな水資源が農業や産業の発展を支えてきました。
市の北東部から南西部にかけて、筑後川が流れている。
ほぼ川に沿って境界が引かれており、筑後川が市内を貫いている部分は少ないという独特な市境を形成しています。
筑後川は九州最大の河川で、久留米市民にとって「母なる川」として親しまれています。
筑後川における上流・中流・下流の区分については国土交通省河川局が作成した「筑後川水系河川整備基本方針」および「筑後川水系河川整備計画」で明記されているように、国の重要な河川として管理されています。
川沿いには肥沃な沖積平野が広がり、古くから米作りが盛んな地域として知られてきました。
九州一の大河筑後川と緑豊かな耳納連山に育まれた筑後平野の肥沃な大地のもと、米麦大豆、野菜、果樹、種苗苗木類、花き、酪農、畜産など多種多様な品目が生産されています。
実際に、久留米市は全国でも有数、かつ県内最大の農業産出額を誇る農業都市として知られています。
久留米市の農業の特徴として、中でもミカン(かんきつ類)の苗木は、愛媛や和歌山など全国の主要産地に出荷され、生産量は日本一を誇ることが挙げられます。
特に田主丸町は温暖な気候や豊かな土壌に加え、先人たちのたゆまぬ技術改良の努力により、苗木の一大産地へと成長した。
町内には「植木苗木発祥の碑」が立つという歴史を持っています。
また、植木・苗木発祥の地と言われ、現在も日本三大植木産地である久留米として、植木の日本四大生産地の1つである、福岡県久留米市。
東西に連なる耳納連山の麓に「くるめ緑花センター」は位置しています。
久留米の植木は豊かな土壌と気象条件に恵まれ、「つつじ」を中心に古くは江戸時代より発展し続けてきました。
三潴地区では特別な農産物も生産されており、三潴地区の特産品は、「黒松、酒、ハトムギ」です。
(黒松)久留米市は、日本三大植木産地のひとつで、特に三潴地区では庭園・観賞用の黒松の生産が盛んです。
この黒松は、百数十年の歴史と伝統があり「みづまの黒松」の名で全国的に有名です。
さらに現在、三潴地域には15軒ほどの植木業者が集まり、黒松の植栽規模は日本一という記録を持っています。
「久留米市って山も川もあって自然豊かなんだ…」と初めて訪れる方も多いでしょう。
市街地は主に筑後川の北岸に発達し、JR久留米駅や西鉄久留米駅を中心に商業施設や住宅地が広がっています。
人口当たりの医師数は、全国トップレベルであり、久留米大学医学部をはじめ PET等の最先端医療設備を持つ施設が集積した高度医療都市であるという一面も持ち合わせています。
南部には田園地帯が広がり、のどかな風景が今も残されています。
三潴地区は九州でトップクラスのハトムギ生産地です。
ハトムギはイネ科ジュズダマ属の穀物で、9〜10月に収穫されますなど、伝統的な農業も継続されています。
このような地形的特徴により、久留米市は都市機能と自然環境がバランスよく調和した、住みやすい街として評価されています。
2005年(平成17年)2月1日 – 市域拡大を記念し「ふるさとのささやき 〜新久留米市の歌〜」を制定、市歌が2曲並立となるなど、市の発展と共に新たな文化も生まれています。
久留米市の気候については、2016年1月25日に久留米アメダス(標高7m)において1977年に統計開始されて以来の最低気温(気象官署・アメダス)となる-65度を記録したという記録もあり、冬季には厳しい寒さになることもあります。
筑後川の治水については、治水事業は江戸時代初期より藩主導で開始されている。
1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いにおいて筑後では久留米城主の小早川秀包と柳河城主の立花宗茂が西軍に加担したため改易され、代わりに石田三成を捕縛する大功を立てたことにより田中吉政が筑後一国・柳河32万石の国主として1601年(慶長6年)に入部したが、吉政は早くも筑後川の改修に取り組んだという長い歴史があります。
現在の久留米市は、2015年11月2日 – 久留米市を中枢都市とし、大川市・小郡市・うきは市・三井郡大刀洗町・三潴郡大木町と「連携中枢都市圏」を形成することを宣言するなど、周辺地域との連携を深めながら、筑後地方の中心都市としての役割を果たしています。
久留米市の気候と季節の移り変わり
久留米市の気候は、年平均気温163℃、年降水量18447mmという恵まれた環境にあり、九州北部の内陸性気候と海洋性気候の影響を併せ持つ特徴的な地域となっています。
気温は1°Cから32°Cの範囲で変化し、-2°C未満や35°Cを超えることは滅多にない穏やかな気候が魅力的な都市といえるでしょう。
春の訪れは早く、3月下旬から桜の開花が始まります。
久留米城跡では、見事な石垣と濠の落ち着いた佇まいにサクラが華を添え、小高い城跡一帯が淡い桃色に染まり、城内にはソメイヨシノ26本、ヤマザクラ13本、陽光桜6本、御衣黄桜3本、八重桜1本の計49本が植えられています。
筑後川沿いでは約200本のソメイヨシノの桜並木が圧巻の景観を作り出し、市民や観光客の憩いの場となっています。
また、浅井の一本桜は幹周り43m、高さ18mの山桜で樹齢約120年といわれ、ため池に映る”逆さ桜”も一見の価値があり、県内外から多くの見物客が訪れる名所となっています。
梅雨時期の6月から7月上旬は、6月の降水量が平均381mmと最も多くなりますが、この時期の久留米市には別の魅力があります。
龍護山千光寺では約7,000株の紫陽花が境内を埋め尽くし、「あじさい寺」として親しまれ、山間の静かな環境で色とりどりの紫陽花を楽しむことができるでしょう。
高良山あじさい園では約4,000株のアジサイが青、紫、白など色とりどりに彩られ、久留米市の「市民とつくる花と緑の名所」に認定されています。
雨に濡れた紫陽花の美しさは、梅雨の憂鬱さを忘れさせてくれる特別な景観を演出しています。
夏本番の7月から8月は、最高気温が35度を超える日もありますが、筑後川からの涼風が市街地に流れ込み、体感温度を和らげてくれる効果があります。
この時期の最大のイベントは8月に開催される「水の祭典久留米まつり」で、明治通りでのマーチングやストリートパフォーマンス、太鼓響演会、1万人のそろばん総踊りなど、市民総出の夏祭りとして盛大に開催されます。
筑後地区最大の夏祭りとして知られ、県内外から多くの観光客が訪れ、久留米の夏の風物詩として定着しています。
秋の10月から11月にかけては、気温が20度前後で安定し、観光に最適な季節を迎えます。
田主丸地区は果物の産地として有名で、巨峰ぶどうや柿、梨などの果物狩りが楽しめる観光農園が点在しています。
耳納連山の紅葉は10月下旬から色づき始め、11月中旬にかけて見頃を迎えるでしょう。
高良山や発心公園などでも美しい紅葉が楽しめ、ハイキングやドライブコースとして人気を集めています。
冬の12月から2月は、最低気温が0度近くまで下がることもありますが、1月の降水量は平均68mmと最も少なく、比較的乾燥した晴天が続きます。
積雪はほとんどなく、九州の温暖な冬の特徴を示しています。
この時期は、久留米絣の工房見学や酒蔵めぐりなど、室内での文化体験が楽しめる季節でもあります。
また、梅の開花が2月下旬から始まり、春の訪れを告げる風物詩となっています。
久留米市の気候は、四季折々の自然の変化を楽しめる恵まれた環境にあり、それぞれの季節に応じた観光資源が豊富に存在しています。
温暖で過ごしやすい気候は、年間を通じて観光客を迎え入れる基盤となっており、久留米市の大きな魅力の一つとなっているのです。
久留米市と隣接する自治体
久留米市は福岡県南部に位置する、人口約30万人を擁する筑後地方の中心都市であり、県内第3位の規模を誇る都市として発展を続けています。
筑後川の恵みに育まれた自然豊かなまちとして知られ、江戸時代には有馬藩の城下町として栄えた歴史を持ちます。
市の位置関係を詳しく見ると、北側は佐賀県鳥栖市、基山町、みやき町と県境を接しており、東側には福岡県うきは市、大刀洗町が隣接。
南側には八女市、広川町、筑後市があり、西側は大川市、柳川市、大木町と接する形で、まさに筑後地方の要衝として機能しています。
特筆すべきは、佐賀県鳥栖市との密接な関係でしょう。
JR鹿児島本線や九州自動車道で結ばれた両市は、通勤・通学圏として一体的な都市圏を形成しており、県境を越えた経済交流が活発に行われています。
「久留米市に住んで鳥栖市で働く」という生活スタイルも定着しており、行政区域を超えた生活圏が形成されている点が大きな特徴となっています。
交通アクセスの面では、九州新幹線とJR鹿児島本線・久大本線、西鉄天神大牟田線・甘木線の計5つの路線が走っており、合計25の駅が存在するなど、鉄道網が充実。
福岡空港から九州新幹線で約17分、福岡空港・博多・天神からわずか30分という優れた立地条件を活かし、九州各地へのアクセス拠点として機能しています。
高速道路については、九州自動車道の久留米インターチェンジが市のほぼ中間地点にあたる東合川地区に位置しており、国道210号等のバイパス網も充実。
市街地へのアクセスも良好で、物流や観光の面でも重要な役割を果たしています。
産業面では、福岡県最大の農業都市として知られ、九州一の大河「筑後川」の恵みを受けた肥沃な筑後平野で様々な農産物が生産されています。
巨峰の産地として知られる田主丸町や、福岡県内では唯一のハトムギの生産地である三潴町など、地域ごとに特色ある農業が展開されています。
伝統工芸品も豊富で、国の重要無形文化財に登録された「久留米絣」は、1800年頃に生まれた手括り藍染めの手織り技術として全国的に有名。
その他にも籃胎漆器、城島鬼瓦、久留米おきあげ、筑後和傘など、多様な工芸品が受け継がれています。
食文化においては、とんこつラーメン発祥の地として知られ、濃厚でクリーミーなスープと細麺の絶妙な組み合わせが特徴的。
また、焼き鳥は人口当たりの店舗数が日本一と言われ、「ダルム」と呼ばれる豚の腸を使った独特の焼き鳥が名物となっています。
医療・教育の充実も久留米市の大きな強みとなっています。
久留米大学病院は地域の中核的な医療機関として高度医療を提供しており、久留米大学医療センターも地域医療に貢献。
これらの医療機関の存在により、安心して暮らせる環境が整備されています。
観光面では、隣接する各市町村との連携を深めており、筑後川流域の自治体と共同で観光ルートを開発したり、広域的な観光PRを展開。
例えば、うきは市の果樹園巡りと久留米市のグルメツアーを組み合わせた観光プランは多くの観光客に人気を集めており、地域全体の魅力向上に貢献しています。
このように久留米市は、恵まれた立地条件と充実した交通インフラを基盤に、農業・工業・商業がバランスよく発展した都市として成長を続けています。
隣接自治体との連携により筑後地方全体の発展を牽引する役割を担いながら、伝統と革新が調和した魅力的な地域づくりを進めている都市と言えるでしょう。
久留米市の歴史と文化を探る
久留米市の歴史と文化は、約2万年前の旧石器時代から現代まで続く悠久の時の流れの中で形成されてきました。
1889年(明治22年)4月1日、市町村制度発足により、日本で最初に市制施行した31市のひとつとして誕生した久留米市。
その長い歴史の中で、様々な時代の痕跡が今も街のあちこちに息づいています。
古代から続く歴史の足跡を辿ると、旧石器時代の石器が発見され、縄文時代には広大な平野に生い茂る照葉樹林と湧き水に恵まれた豊穣の地として栄えていたことが分かります。
古代日本最大の内乱、磐井の乱の最後の戦場となったという歴史的事実も、この地の重要性を物語っています。
古墳が多いのは、古代から人口が多く住みやすい地域だった証拠であり、現在でも学校の遠足で訪れるほど市民にとって身近な存在となっています。
江戸時代に入ると、久留米の歴史は大きな転換期を迎えます。
元和7年(1621)、有馬豊氏が久留米城を基に整備をはじめ、4代頼元の頃まで約70年をかけ、東は現久留米大学病院の西半分、南は現久留米市役所付近まで広がる城を完成させました。
1620年以降幕末まで有馬家が藩主を務め、21万石を領した久留米藩。
初代久留米藩主の有馬豊氏は、元は京都府の丹波国福知山藩8万石の大名でしたが、今からちょうど400年前、久留米藩21万石に移封。
以降250年にわたり、この地を有馬家が治め、町の整備、学問の奨励などをすすめ、久留米市発展の礎を築いたのです。
有馬家の功績は城下町の整備だけにとどまりません。
およそ500mの間に17寺院が建ち並ぶ同市寺町。
江戸時代には最大で25の寺院があったといわれており、中には、豊氏が京都から呼んだ寺もあるという文化的遺産も残されています。
高良大社は、筑後国の一ノ宮で、本殿、幣殿、拝殿は、久留米藩3代藩主有馬頼利の寄進により、造営されたもので、国の重要文化財に指定されており、水天宮は、壇ノ浦の戦いで破れた安徳天皇と平家一門の霊を祀る祠を建てたことに由来し、江戸時代になって、久留米藩2代目藩主である有馬忠頼が現在の場所へ移転したという歴史を持ちます。
久留米市が誇る伝統工芸の中でも特筆すべきは久留米絣でしょう。
江戸時代の後期に、井上伝という当時12歳の少女が創始したとされ、久留米藩が産業として奨励していた。
一時は年間200〜300万反を生産した久留米絣。
1957年に、木綿では初めて、国の重要無形文化財として指定され、紺地に白く織り出される模様は、きわめて単純で素朴ながら強い健康な表現力があって、染織美術に高い位置を占めると評価されています。
タテ糸とヨコ糸の絣を合わせて織りながら柄を作る、全工程が手間と時間のかかる手仕事で、世界的にも希少な織物で、制作には緻密な計算と卓抜した技量が必要な芸術品といえるでしょう。
明治以降の久留米市は、近代産業都市として大きく発展します。
特に注目すべきは、石橋正二郎が1889年、福岡県久留米市に生まれ、17歳のとき家業の仕立物屋を継ぎ、地下足袋の創製やゴム靴の製造を通じて全国的な企業へと拡大。
1931年にはブリッヂストンタイヤ株式会社(現・株式会社ブリヂストン)を創業し、自動車タイヤの国産化に成功したことです。
1931年3月1日に石橋正二郎によって福岡県の久留米市で創業されたブリヂストンは、今や世界的企業となりました。
石橋正二郎の功績は実業だけではありません。
1927年に九州医学専門学校(現 久留米大学医学部)へキャンパスの敷地、約10,000坪と鉄筋コンクリート造校舎を寄付、1956年4月には久留米市へ石橋文化センターを寄付。
約30,000平方メートルの敷地に石橋美術館(2016年より久留米市美術館)、体育館(現在は図書館)、プール、文化会館、野外音楽堂、遊園地など置かれた巨大な総合文化施設を建設しました。
「世の人々の楽しみと幸福の為に」という言葉には、企業経営と文化事業を通じて社会に貢献した正二郎の、生涯にわたる強い想いが込められています。
現在の久留米市は、福岡市、北九州市に次いで、県内3位の人口約30万人が暮らす中核都市。
筑後地域商業の中心地として発展を続けています。
広大な平野を悠々と流れる九州一の河川・筑後川は、古くから地域の人々が誇る久留米のシンボル。
地域に清らかな水をもたらし、河川敷は憩いの場となっており、市街地から少し離れた東部には、東西約30kmにわたって山々が連なる耳納連山があり、一直線にのびる稜線は屏風に例えられるほどの美しさを誇ります。
文化芸術の分野でも久留米市は輝かしい歴史を持ちます。
青木繁、坂本繁二郎、古賀春江、高島野十郎、吉田博らが久留米に生まれ、明治~昭和の日本洋画壇で活躍し、2016年に開館した「久留米市美術館」では、久留米出身の画家の作品を中心とするコレクションを形成しています。
また、昭和以降では、音楽・芸能の分野で特に活躍が目覚ましく、「上を向いて歩こう」を作曲した中村八大、チェッカーズ(藤井フミヤ)、松田聖子などのミュージシャンや、田中麗奈、吉田羊などの俳優が久留米出身者として全国的に知られています。
久留米市の歴史と文化は、古代から現代まで脈々と受け継がれてきた貴重な遺産です。
筑後川の恵みを受けた肥沃な大地、江戸時代の有馬藩による城下町の発展、久留米絣に代表される伝統工芸、そして石橋正二郎によるゴム産業の興隆と文化事業への貢献。
これらすべてが織りなす重層的な歴史と文化が、現在の久留米市の魅力を形作っているのです。
訪れる人々は、街角に残る歴史の痕跡を辿りながら、この街が歩んできた豊かな物語に触れることができるでしょう。
久留米市の歴史的背景
久留米市は古代から現代まで、九州北部の要衝として重要な役割を果たしてきました。
弥生時代の遺跡が市内各地で発見されており、この地域に早くから人々が定住していたことが分かります。
特に筑後川流域の肥沃な土地は、稲作文化の発展に大きく貢献しました。
江戸時代には久留米藩21万石の城下町として栄え、有馬氏が約250年にわたって統治。
この時代に確立された町割りや文化は、現在の久留米市の基礎となっています。
「もしかすると、街を歩いていて感じる独特の雰囲気は、この歴史の重みからくるものかもしれない…」と感じる方も多いでしょう。
明治維新後は軍都として発展し、陸軍の師団が置かれたことで近代化が急速に進みました。
戦後は平和産業都市への転換を果たし、ゴム産業を中心に工業都市として成長。
現在では医療・バイオ産業の集積地としても注目を集めています。
歴史的な変遷を経て、久留米市は伝統と革新が共存する魅力的な都市へと発展しました。
久留米市の行政と市政の変遷
久留米市は1889年(明治22年)4月1日の市制施行以来、福岡県南部の中核都市として着実な発展を遂げてきました。
市制施行時は日本で最初に市制施行した31市のひとつでありながら、当時は日本で一番人口の少ない市でした。
明治時代の市制施行当初は人口約2万人の小規模な都市でしたが、現在では福岡市、北九州市に次いで福岡県では第3位、九州全体では第8位の人口を擁する中核市となりました。
2024年2月に人口減少により30万人を割り込んだものの、依然として筑後地方の中心都市としての地位を保っています。
市政の大きな転換点となったのは、2005年(平成17年)2月5日の平成の大合併でした。
三井郡北野町・三潴郡三潴町・三潴郡城島町・浮羽郡田主丸町を編入し人口が30万人を突破しました。
福岡県の資料によると、久留米市・旧田主丸町・旧北野町・旧城島町・旧三潴町が平成17年2月5日に合併したことが確認されています。
この合併により、市域は東西約32km、南北約16kmとなり、東西に長い自治体となりました。
市域の拡大は、久留米市が福岡県内で3番目の人口規模を持つ都市となる基盤を築きました。
行政組織の変遷も注目に値する点があります。
戦後の地方自治法施行により、市民による直接選挙で市長を選出する制度が確立されました。
2001年(平成13年)4月1日には特例市に指定され、さらに2008年4月1日に中核市に移行しました。
中核市への移行は久留米市にとって重要な意味を持ちました。
県から多くの権限が移譲され、保健所の設置や都市計画の決定など、より地域の実情に即した行政サービスの提供が可能となりました。
「市民との協働によるまちづくり」を掲げ、住民参加型の行政運営が進められています。
近年の市政では、以下の重点施策が推進されています。
中心市街地活性化の取り組みとして、2016年(平成28年)4月、久留米井筒屋・六角堂広場跡地に久留米シティプラザが落成しました。
延床面積34,54833㎡、地上6階地下2階の規模を持つ総合文化施設で、劇場、店舗、集会場などの機能を有し、都市機能の充実を図る重要な拠点となっています。
平成20年3月12日付けで「久留米市中心市街地活性化基本計画」が内閣総理大臣により認定され、計画的な中心市街地の再整備が進められてきました。
医療都市構想については、久留米大学病院を中心とした医療産業の集積を目指しています。
人口当たりの医師数は全国トップレベルであり、久留米大学医学部をはじめPET等の最先端医療設備を持つ施設が集積した高度医療都市となっています。
久留米大学病院は一般病床数1,045床、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、ドクターヘリ、PETを備え、聖マリア病院は一般病床数1,129床、救命救急センター、総合周産期母子医療センター、PET、高気圧酸素治療を有するなど、充実した医療環境が整備されています。
子育て支援の充実では、待機児童ゼロを目標に、保育施設の整備が進められています。
若い世代が安心して子育てできる環境づくりに力を入れ、人口減少対策としても重要な施策となっています。
2015年11月2日には久留米市を中枢都市とし、大川市・小郡市・うきは市・三井郡大刀洗町・三潴郡大木町と「連携中枢都市圏」を形成することを宣言しました。
広域連携により、地域全体の発展を目指す新たな取り組みが始まっています。
久留米市は今後も、筑後地域の中心都市として更なる発展が期待されています。
歴史ある都市としての伝統を守りながら、時代のニーズに応じた新しいまちづくりを進め、住民の生活の質の向上と地域経済の活性化を両立させる取り組みが続けられています。
久留米市の文化財と名所
久留米市には、国や県が指定する貴重な文化財が数多く残されています。
特に注目すべきは、国の重要文化財に指定されている梅林寺の本堂と山門でしょう。
江戸時代初期に建立されたこれらの建造物は、当時の建築技術の粋を集めた傑作として知られています。
市内には約150件もの指定文化財が点在しており、その多くが一般公開されているのが特徴です。
水天宮の本殿は、全国の水天宮の総本宮として多くの参拝者を集めています。
「久留米市の歴史を肌で感じたい」という方には、高良大社の参道を歩くことをおすすめします。
名所として外せないのが、久留米城跡を中心とした篠山神社一帯のエリア。
春には約200本の桜が咲き誇り、市民の憩いの場として親しまれています。
また、坂本繁二郎生家は、日本近代洋画の巨匠の生涯を知る貴重な施設として整備されました。
文化財巡りには、久留米市が発行している「文化財マップ」が便利です。
主要な文化財の位置と解説が記載されており、効率的に見学できるルートも提案されています。
これらの文化財は、久留米市の歴史と文化を今に伝える大切な宝物といえるでしょう。
久留米市の観光スポットTOP10
久留米市には、歴史と自然、文化が融合した魅力的な観光スポットが数多く存在します。
九州の中心都市として発展してきた久留米市は、筑後川の恵みを受けながら独自の文化を育んできました。
古い歴史を持つ神社仏閣から、現代的な文化施設、豊かな自然を楽しめる公園まで、幅広い世代が楽しめる観光地が点在しているのが特徴でしょう。
久留米市を訪れる観光客は年間約500万人を超え、その人気は年々高まっています。
特に久留米ラーメンの発祥地として全国的に知られ、グルメを目的に訪れる方も少なくありません。
また、ゴムタイヤ産業の中心地としての産業観光や、筑後川沿いの美しい景観、四季折々の果物狩りなど、多様な観光資源が訪問者を魅了し続けているのです。
これから紹介するTOP10の観光スポットは、久留米市の魅力を存分に味わえる場所ばかり。
歴史的建造物から自然豊かな公園、文化施設まで、それぞれに異なる魅力があります。
以下で詳しく解説していきます。
1.久留米城跡
久留米市のシンボルとして親しまれる久留米城跡は、筑後川を望む高台に位置する歴史的名所で、村上源氏の流れを汲む有馬氏が約250年にわたって治めた久留米藩の中心地でした。
江戸時代に有馬氏の居城として栄えた城は、元和7年(1621年)3月18日に有馬豊氏が入城した際、一国一城令により櫓や本丸などが破却されており、雨露を凌ぐ場所さえない「名ばかりの城」となっていた状況から、豊氏による大改修が始まりました。
豊氏はこの城を基に整備をはじめ、4代頼元の頃まで約70年をかけ、東は現久留米大学病院の西半分、南は現久留米市役所付近まで広がる城を完成させたのです。
有馬氏の始まりは、播磨国の名門・赤松家の4代目当主「赤松則村」の孫「赤松義祐」が摂津国の有馬郡に渡ったことが契機でした。
豊氏は細川澄元の曾孫にあたるという名門の血筋を持ち、慶長19年(1614年)からの大坂の陣においても徳川方として参戦して功を挙げ、元和6年(1620年)12月8日、筑後久留米に21万石に加増転封され、国持ち大名となったという経緯があります。
久留米城の本丸は、2階建の長い櫓でぐるりととり囲み、隅々には7つの櫓が建てられていました。
中でも巽櫓は3層で一番大きく、天守の役目をはたしていたという壮大な構造を誇りました。
明治時代の廃城令により取り壊されましたが、現在も石垣や堀の一部が残され、本丸南面に高石垣が残っており、片方の石垣には反りがあり、もう片方は直線的という特徴的な構造を見ることができます。
春にはソメイヨシノ(26本)、ヤマザクラ(13本)、陽光桜(6本)、御衣黄桜(3本)、八重桜1本(計49本)が咲き誇り、多くの花見客で賑わう人気スポットとなっています。
特に御衣黄桜は緑色の花を咲かせる珍しい品種で、4月中旬頃に見頃を迎えます。
「ここから見る筑後川の眺めは格別かもしれない…」と感じる方も多いのは、久留米城は筑後川を天然の堀として利用していた立地の良さによるものでしょう。
城跡からは久留米市街地を一望でき、特に夕暮れ時の景色は息をのむ美しさを誇ります。
現在の城跡は明治10年に、地域の復興と安寧を願って建てられた篠山神社の境内となっています。
1874年(明治7年)の廃城令によって廃城処分となり、本丸御殿を含むすべての建物は撤去されましたが、その後、1877年(明治10年)に本丸御殿跡地に旧藩士・領民によって有馬家への追慕・感謝のために篠山神社が建立されました。
篠山神社には有馬豊氏命(初代藩主)、有馬頼撞命(第7代藩主)、有馬頼永命(第10代藩主)、有馬頼咸命(第11代藩主)、有馬頼寧命(第14代当主、農林大臣、中央競馬会理事長)の5柱が祀られています。
有馬頼寧氏は競馬の有馬記念の名前の由来となった人物でもあります。
境内には昭和35年に市制70周年を記念し、郷土資料の調査・研究を目的に、当時の株式会社ブリヂストン社長・石橋正二郎氏より寄贈された有馬記念館があり、有馬家ゆかりの歴史資料や美術工芸品を中心に展示公開しています。
また、郷土史における重要な出来事や偉人を称える巨大な石碑がいくつも建立され、境内を歩く人々が歴史を顧みる一助となっています。
散策路も整備され、ゆっくりと歴史に思いを馳せながら歩けるのが魅力となっており、本丸東には蜜柑丸という腰曲輪がありました。
名の由来は蜜柑が植えられていたからという興味深い歴史も残されています。
アクセスも良好で、JR久留米駅から徒歩約15分、西鉄久留米駅からは徒歩約20分で到着し、JR/西鉄「久留米駅」より西鉄バス(3・6・8・9・24・52)番利用「大学病院」下車、徒歩3分という公共交通機関でのアクセスも便利です。
駐車場も約15台(境内ロータリー約7台、石垣下東側駐車場約8台)完備されているため、車での訪問も可能でしょう。
入場料は無料で、年中無休で開放されているため、いつでも気軽に立ち寄れます。
久留米市の歴史を感じながら、四季折々の自然も楽しめる久留米城跡は、筑後国一の宮として崇敬される高良大社、石橋文化センター、久留米市鳥類センターや福岡県青少年科学館など、ファミリー向けの施設も充実している久留米市の観光の第一歩として最適な場所といえます。
有馬豊氏が久留米入城に伴い、瓦職人を呼び寄せたことに始まる城島瓦や、およそ500mの間に17寺院が建ち並ぶ同市寺町など、有馬氏が築いた文化遺産は今も久留米市内各所に残り、久留米市の発展の礎となった有馬家の功績を今に伝えています。
2.石橋文化センター
石橋文化センターは、久留米市の文化芸術の中心地として多くの市民に愛されている複合文化施設です。
1956年に株式会社ブリヂストンの創業者・石橋正二郎氏の寄贈により開園しました。
広大な敷地内には美術館、音楽ホール、図書館、日本庭園などが点在し、「文化と自然が調和した空間を楽しみたい」という方にぴったりの観光スポットとなっています。
特に注目すべきは、四季折々の花々が楽しめる庭園エリアでしょう。
春には約150本の桜、初夏にはバラ園の約400種2,600株のバラが見頃を迎えます。
秋には紅葉、冬には椿や梅が咲き誇り、一年を通じて美しい景観が広がっているのが魅力。
施設内の石橋美術館では、青木繁や坂本繁二郎など久留米ゆかりの画家の作品を中心に、国内外の名作を鑑賞できます。
また、石橋文化ホールでは年間を通じてコンサートや演劇などの公演が開催され、市民の文化活動の拠点として機能。
アクセスも良好で、西鉄久留米駅からバスで約15分、JR久留米駅からは約5分という立地にあります。
入園料は無料(美術館は別途料金)なので、気軽に訪れることができるのも嬉しいポイントでしょう。
3.久留米市美術館
久留米市美術館は、福岡県久留米市の文化と芸術の中心として、地域の人々に深く愛され続けている美術の殿堂といえるでしょう。
1956(昭和31)年に株式会社ブリヂストンの創業者である石橋正二郎・名誉市民から郷土久留米市に寄贈された石橋文化センターの中核施設として、その歴史を刻んできました。
石橋正二郎氏は、世界的タイヤメーカー・ブリヂストンの創業者であり、久留米市出身の実業家として知られています。
彼の「世の人々の楽しみと幸福の為に」という理念のもと、故郷への恩返しとして文化施設を寄贈したことが、現在の久留米市美術館の礎となりました。
1977年には外壁の老朽化に伴い、石橋家の寄付金5億円を基に改装が行われ、1978年に再開館。
その後も時代とともに進化を続け、2016年11月19日に久留米市美術館として新たなスタートを切りました。
美術館の収蔵品は、久留米が誇る芸術家たちの作品を中心に構成されています。
特に注目すべきは、青木繁(1882-1911)と坂本繁二郎(1882-1969)という、同じ年に久留米に生まれた二人の巨匠の作品群でしょう。
青木繁は、若くして日本美術史上に残る名作を描き、重要文化財でもある代表作「海の幸」、「わだつみのいろこの宮」などの鮮烈な作品を残して、28歳で夭逝しました。
その短い生涯の中で、神話や伝説を題材にした浪漫主義的な作品を多く残し、日本近代洋画史に大きな足跡を刻みました。
青木と同じ1882年に久留米市に生まれた坂本繁二郎は、対照的に87歳まで長寿を全うし、第二次大戦後は梅原龍三郎、安井曾太郎と並ぶ洋画会の巨匠と見なされるようになり、1956年には文化勲章を受章しました。
坂本の代表作「放牧三馬」は、1932年に制作された油彩画で、久留米市美術館の至宝の一つとして大切に保管されています。
ヨーロッパ留学までは牛を、帰国後は馬を、戦後は身の回りの静物、なかでも能面を、最晩年は月をおもにテーマとして取り上げました。
その静謐で深い精神性を感じさせる作風は、多くの人々を魅了し続けています。
二人の関係性も興味深いものがあります。
幼児から「神童」と持てはやされていた坂本は、青木の画技の上達ぶりに驚嘆し、絵の面で青木に追い抜かれてなるものかというライバル意識から、上京を決意したといわれています。
青木が早逝した後、坂本は青木の遺作展の開催や画集の刊行のために奔走したことからも、二人の深い友情と相互の尊敬の念がうかがえます。
久留米市美術館では、これらの貴重な作品を中心に、九州ゆかりの作家による絵画や彫刻など約1,000点を収蔵。
常設展示では季節ごとにテーマを変えて公開され、訪れるたびに新しい発見があります。
建物自体も見どころの一つとなっています。
設計は菊竹清訓が担当したモダンな建築は、開放的な展示空間を実現し、アートとの距離を縮める工夫が随所に施されています。
自然光を効果的に取り入れた展示室は、作品本来の色彩や質感を最大限に引き出し、鑑賞者に深い感動を与えます。
企画展も充実しており、2025年5月24日から8月31日まで開催される「異端の奇才 ビアズリー展」では、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)の協力により、19世紀末の英国画家オーブリー・ビアズリーの作品約200点が展示される予定となっています。
国内外の優れた美術作品に触れる機会が豊富に用意されているのも、久留米市美術館の大きな魅力といえるでしょう。
美術館が位置する石橋文化センターは、バラやツバキなど四季折々の花が彩る広大な庭園を有し、久留米市美術館をはじめ、音楽ホールや図書館を備える複合文化施設として機能しています。
石橋文化センターには、開園間もない頃よりバラ園があり、バラは石橋文化センターのシンボル的な花となっています。
春には400品種2,600株のバラが咲き誇り、園内は甘い香りに包まれます。
石橋正二郎氏自らの構想による回遊式の日本庭園も見事で、耳納連山の山石も使用された本格的な造りとなっています。
初春の梅、初夏の新緑、秋の紅葉と、四季を通じて様々な表情を見せる庭園は、美術鑑賞の前後に散策を楽しむのに最適な環境を提供しています。
館内にはカフェも併設されており、日本庭園を望むカフェ&ギャラリーショップ「楽水亭」という名前は、建設・寄贈者である石橋正二郎氏の揮毫「楽山愛水」に由来しています。
美術鑑賞後、庭園を眺めながらゆったりとした時間を過ごすことができるのも、久留米市美術館の魅力の一つでしょう。
アクセスも便利で、JR久留米駅より西鉄バスで15分、西鉄久留米駅より5分(文化センター前下車)、車では久留米インターより10分という立地にあります。
駐車場も完備されており、家族連れでも気軽に訪れることができます。
入館料は一般500円とリーズナブルで、中学生以下は無料という点も、市民に開かれた美術館としての姿勢を示しています。
美術を身近に感じてもらいたいという理念が、料金設定にも反映されているといえるでしょう。
久留米市美術館は、単なる美術作品の展示施設にとどまらず、地域の文化的アイデンティティを形成する重要な拠点として機能しています。
久留米が生んだ偉大な芸術家たちの作品を通じて、地域の歴史と文化を次世代に伝える役割を担っているのです。
石橋正二郎氏の理念である「世の人々の楽しみと幸福の為に」という精神は、今も美術館の運営に息づいており、久留米市の文化的な一面を体験するなら、ぜひ訪れたいスポットといえるでしょう。
4.久留米市鳥類センター
久留米市鳥類センターは、福岡県久留米市の中央公園内にある、九州でも珍しい鳥類専門の動物園として、家族連れから観光客まで幅広い世代に愛されている観光スポットとなっています。
久留米市東櫛原町1667に位置し、みどり豊かな30,000平方メートル(市民流水プール9,000平方メートル含む)の敷地を誇る広大な施設となっています。
約80種400点の鳥や動物を飼育している全国でも珍しい動物園として知られ、約90羽ものクジャクを主体に、タンチョウやフラミンゴなど約80種420点もの鳥類が見られます。
園内の生き物たちの魅力について詳しく見ていきましょう。
まず目玉となるのが、インドクジャクで、昔は「1000羽クジャク」として、久留米の名物となりましたが、現在では敷地面積や飼育環境を考慮して、80羽程度の飼育数を維持しています。
クジャクの美しい羽根は毎年生えかわり、夏の初め頃には抜けてしまい、また冬の終わり頃から揃い始めます。
羽根を広げる姿はお天気の日よりは薄曇りの日、風のない時が多いという興味深い習性があります。
水鳥エリアでは、鳥類センター内水鳥のドーム内で最大の鳥で、羽根を広げると2~3mくらいあるモモイロペリカンや、ピンク色は、食べ物によるもので、専用のエサをあげているフラミンゴが観察できます。
フラミンゴの有名な片足立ちは体温調節のためと言われており、向かい合うとハート形に見える首の形は写真撮影の人気スポットとなっています。
希少な鳥類も多く飼育されており、国の特別天然記念物の他、ワシントン条約附属書、渡り鳥条約等、数々の希少種の指定を受けているタンチョウは、もともとは、中国の合肥市から友好の証として贈られたのが始まりで、繁殖能力が高く毎年のようにヒナが順調に育っているそうです。
施設の充実した設備も大きな魅力となっています。
観覧車は高さ約60メートルから久留米市街を一望でき、「鳥になった気分を味わえる」と評判を呼んでいます。
遊園地・ふれあいコーナーは、16:30で終了となりますが、メリーゴーランドやゴーカートなど小さな子ども向けの遊具が充実しており、家族で一日中楽しめる環境が整っています。
ふれあい体験も充実しており、日曜日・祝日(午前の部)10時より(午後の部)14時より定員は各部で30名程度でモルモットやパンダマウスなどとのふれあい体験ができます。
リスザル、フラミンゴなどに直接エサやりができたり、第1・3日曜には「モルモットのふれあい教室」を、第2日曜には「ペンギンのお食事タイム」を開催しており、動物との距離が近い体験型の施設として人気を集めています。
夏季限定の流水プールは、久留米市民にとって夏の風物詩となっています。
プール営業期間は午後6時まで開園(入園は午後5時30分まで)と営業時間も延長され、動物園とプールの両方を楽しめる複合レジャー施設として賑わいを見せています。
アクセス面でも便利な立地にあります。
西鉄バス「科学館前」下車徒歩3分、西鉄大牟田線「西鉄櫛原駅」下車徒歩5分と公共交通機関でのアクセスが良好で、車の場合は九州自動車道・久留米IC下車、約10分という好立地にあります。
駐車場も無料で利用できるため、車での来園も気軽にできます。
料金体系も大きな魅力の一つで、2025年4月1日より大人・高校生350円、中学生以下無料という非常にリーズナブルな設定になっています。
障がい者は無料(介護者1名も無料)となっており、誰もが気軽に訪れることができる施設となっています。
休園日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、夏期プール営業期間中は休園日なし、12月29日~1月1日となっており、年間を通じて多くの日に開園しています。
久留米市の観光における位置づけとしても重要な施設となっています。
久留米市は福岡県内でも有数の観光都市として、年間を通じて多くの観光客が訪れており、久留米市鳥類センターや福岡県青少年科学館など、ファミリー向けの施設も充実しており、子供から大人まで楽しめる環境が整っています。
歴史的な背景も興味深く、1954年1月1日に久留米市役所近くの三本松公園に、市民手作りの、市営で無料の久留米市動物園が開園したのが始まりで、その後1969年10月には「三本松動物園」は閉鎖されて、動物園は1970年1月に中央公園に移転しました。
戦後の荒廃した社会情勢のなか、子どもたちの心を癒す動物園づくりを目指し開園したもので、2012年現在もその思想を受け継ぎ、「見せる」だけの動物園から「ふれあい」のできる動物園として運営されています。
教育面での取り組みも充実しており、命の大切さ、尊さを学ぶ動物愛護思想の啓発普及事業として、学校現場等においては動物愛護を学べる事業(移動動物園、ゲストティーチャー、職場体験受入など)や市民との協働による生涯学習(バードボランティア・サポーター)も行っています。
久留米市鳥類センターは、単なる観光施設にとどまらず、地域の教育、文化、レクリエーションの拠点として、久留米市民の憩いの場、そして観光客にとっても手軽に楽しめる観光スポットとして、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。
リーズナブルな料金設定と充実した施設内容、そして動物たちとの触れ合いを通じて、訪れる人々に癒しと学びの機会を提供し続けています。
5.久留米市中央公園
久留米市中央公園は、市民の憩いの場として親しまれている都市公園です。
JR久留米駅から徒歩約15分の好立地にあり、約23ヘクタールの広大な敷地を誇ります。
園内には、子供向けの大型遊具が設置された「冒険広場」や、四季折々の花々が楽しめる「花壇エリア」があるでしょう。
特に春には約200本の桜が咲き誇り、花見スポットとして多くの人で賑わいます。
「家族でピクニックを楽しみたいけれど、どこがいいかな…」と悩む方にとって、芝生広場は理想的な場所となるはずです。
公園の特徴的な施設として、以下のものが挙げられます。
– 野外ステージ 市民イベントやコンサートが定期的に開催され、地域交流の拠点となっています。
– スポーツ施設 テニスコートや多目的グラウンドがあり、予約制で利用可能です。
– 散策路 全長約2キロメートルのウォーキングコースが整備されています。
また、園内には久留米市鳥類センターも隣接しており、一日中楽しめる観光エリアとなっています。
駐車場も約300台分完備されているため、車でのアクセスも便利でしょう。
久留米市中央公園は、自然と都市機能が調和した、市民と観光客の両方に愛される空間となっています。
6.田主丸の観光果樹園
久留米市の田主丸地区は、九州有数のフルーツ王国として知られる観光果樹園の宝庫です。
年間を通じて様々な果物狩りが楽しめることから、家族連れやカップルに大人気のスポットとなっています。
春から初夏にかけては、いちご狩りが最盛期を迎えます。
「あまおう」をはじめとした福岡県産の高級品種を、その場で摘み取って味わえる贅沢な体験ができるでしょう。
6月から8月にかけては、ぶどう狩りのシーズンが到来。
巨峰やピオーネ、シャインマスカットなど、20種類以上の品種を栽培する農園が点在しています。
秋になると、梨や柿、みかんなどの収穫体験が楽しめます。
「もしかしたら、こんなに新鮮な果物を食べたのは初めてかもしれない…」と感動する方も多いはず。
田主丸の観光果樹園では、以下のような魅力的な体験ができます。
– 時間無制限の食べ放題プラン 多くの農園で採用されており、ゆっくりと果物狩りを満喫できます。
– 農家直伝の美味しい果物の見分け方講座 プロの目利きを学べる貴重な機会です。
– お土産用の果物直売所 市価よりもお得な価格で新鮮な果物を購入できます。
各農園では、車椅子対応やペット同伴可能な施設も増えており、誰もが楽しめる環境が整っています。
田主丸の観光果樹園は、久留米市の自然の恵みを五感で体験できる、まさに必訪スポットといえるでしょう。
7.久留米ラーメンの名店
久留米市を訪れたら必ず味わいたいのが、全国的にも有名な久留米ラーメンです。
豚骨スープの発祥地として知られる久留米市には、創業70年を超える老舗から新進気鋭の店まで、約200軒ものラーメン店がひしめき合っています。
久留米ラーメンの特徴は、濃厚でコクのある白濁した豚骨スープと、中細ストレート麺の絶妙な組み合わせ。
「もしかしたら初めての方には濃すぎるかも…」と心配になるかもしれませんが、実は意外とあっさりとした後味が特徴的です。
代表的な名店をいくつかご紹介しましょう。
– 大砲ラーメン本店 昭和28年創業の老舗で、久留米ラーメンの代名詞的存在。
伝統の呼び戻しスープが自慢です。
– 丸星ラーメン店 地元民に愛される昭和33年創業の名店。
あっさりめのスープが女性にも人気。
– モヒカンらーめん 濃厚な豚骨スープと太麺が特徴。
ボリューム満点で若い世代から支持を集めています。
各店舗では替え玉システムも充実しており、お腹いっぱい楽しめるのも魅力的。
久留米市内のラーメン店巡りは、観光の合間の楽しみとしても最適でしょう。
8.筑後川の自然と風景
筑後川は九州最大の河川として、久留米市の自然景観を代表する存在です。
全長143キロメートルに及ぶこの大河は、久留米市を東西に横断し、四季折々の美しい風景を市民や観光客に提供しています。
特に注目したいのが、河川敷に広がる広大な緑地帯でしょう。
春には菜の花が一面に咲き誇り、黄色い絨毯のような光景が広がります。
夏になると、涼を求める家族連れで賑わい、バーベキューや水遊びを楽しむ姿が見られるのも筑後川の魅力。
「こんなに身近に大自然があったなんて…」と驚く観光客も少なくありません。
筑後川沿いには、サイクリングロードも整備されています。
全長約32キロメートルのコースは、初心者から上級者まで楽しめる設計になっており、レンタサイクルも利用可能。
河川敷から眺める夕日は格別で、オレンジ色に染まる空と川面のコントラストは息をのむ美しさでしょう。
また、毎年8月5日に開催される筑後川花火大会は、西日本最大級の規模を誇ります。
約1万8000発の花火が夜空を彩り、45万人もの観客が訪れる一大イベント。
筑後川の雄大な自然は、久留米市の観光において欠かせない存在として、多くの人々に愛され続けています。
9.久留米市の神社仏閣
久留米市は、福岡県南部の筑後地方に位置する歴史と文化が息づく都市であり、数多くの神社仏閣が点在しています。
その中でも特に注目すべき寺社について、詳しくご紹介いたします。
全国総本宮水天宮 – 安産と子育ての守り神
久留米市瀬下町の筑後川のすぐ側に鎮座する全国総本宮水天宮は、日本全国やハワイ等各地に鎮座する水天宮の総本宮となっています。
創建は建久初年(1190年)と伝えられ、平家が壇ノ浦の戦いで破れた後、安徳天皇の母である高倉平中宮に仕えていた女官・官女按察使局伊勢が千歳川(現筑後川)の辺り鷺野ケ原に逃れ来て、安徳天皇の祖母に当たる二位尼を祀って祠を建てたのが水天宮の始まりとされています。
御祭神は天御中主神をはじめ平家ゆかりの安徳天皇、高倉平中宮(建礼門院、平徳子)、二位の尼(平時子)の4柱の神をお祀りしています。
水天宮は名称に『水』がついていることもあり、人々の生活に欠かせない存在である水にまつわるご利益が多く、特にこの全国総本宮の水天宮は、すぐそばに筑後川が流れており、「小さな子どもが溺れないように。
子どもが安全に過ごせるように」という願いから、安産祈願・子宝などの子供に対するご利益があるとされています。
慶安3年(1650年)2代藩主有馬忠頼公の時、筑後川に臨む現在地に移されました。
境内には、水天宮の第22代宮司でもあった眞木和泉守保臣命こと真木保臣をはじめ、一門及び門下生12人と、天王山にて共に自刃された16烈士を奉斎する眞木神社があり、彼の銅像と幽居した「山梔窩」の摸式家屋も建てられています。
水天宮の例大祭は5月5日であり、縁日は毎月5日となっています。
毎年8月に開催される西日本随一の規模を誇る「筑後川花火大会」は、水天宮の奉納花火として始まり、350年以上の歴史をもつことでも知られています。
成田山久留米分院 – 交通安全祈願の聖地
身代り不動尊で全国的に知られている千葉県の大本山成田山新勝寺から御分霊を招請して開山した成田山久留米分院は、1958年成田山新勝寺の分霊を招いて設立されました。
交通安全祈願で有名なこの寺院は、毎年多くの人々が車のお祓いに訪れる場所となっています。
この寺院の最大の特徴は、救世慈母大観音像(総工費20億円)で、高さ62mの鉄筋コンクリート造り、眉間の白毫は30cmの金の延板上に3カラットのダイヤモンド18個が、また胸の瓔珞には水晶と翡翠(56個)を配し、13mの幼児を抱いています。
その大きさは近隣を通る九州自動車道からもはっきり確認できるほどの迫力を誇ります。
胎内は螺旋状の階段で登れ、眺望窓があり遠く雲仙も望め、胎内から地下道を通り光明閣洞窟に行け、また88段の総大理石の階段は新しい名所として話題になっており、「地獄極楽館」も人気を集めています。
久留米市民にとって、新車購入時の交通安全祈願は欠かせない習慣となっており、地域の安全を守る重要な役割を果たしています。
梅林寺 – 久留米藩主有馬家の菩提寺
JR久留米駅のすぐ裏手、筑後川べりの丘に堂々たる伽藍をみせているのが、臨済宗妙心寺派の梅林寺です。
1621年、有馬豊氏が久留米藩の初代藩主として京都の瑞巌寺をこの地に移したことが始まりとなっています。
関が原の戦いで功を為した有馬豊氏公は久留米の土地を与えられ、当時有馬家の領土丹波篠山にあった瑞厳寺を移建し、その名を父則頼公の戒名「梅林院殿」にちなんで「梅林寺」としました。
岐阜県の妙法山正眼寺と共に修行の厳しさで知られ、この梅林寺からは香夢室など、本山、妙心寺の管長も出しているという、九州一の修行道場として名高い寺院です。
寺宝は六百余点を数え、絹本著色釈迦三尊像(重要文化財)のほか、尾形光琳の富士山の図、長谷川等伯の屏風、狩野が描く襖絵なども収蔵されています。
本堂正面に建つ唐門は勅使門とも呼ばれ、明治20年(1887)建築で、伝統的な平唐門の形式に精緻な彫刻で満たされた装飾意匠が秀逸となっています。
梅林寺外苑は、観梅時期には約30種500本、白梅・紅梅・枝垂梅の花が咲き誇り、2月から3月にかけて多くの観梅客で賑わいます。
寺と塀で区切られているが、筑後川側から北側にかけて隣接する梅林寺外苑には市民らが寄進した約30種500本の梅と、多数の久留米ツツジなどが植えられ、市民の憩いの場となっています。
高良大社 – 筑後国一の宮
耳納連山の最端、標高312メートルの高良山に鎮座するのが、旧国幣大社で筑後国一の宮である高良大社です。
高良玉垂宮の創建は、履中天皇元年(400年)と伝えられ、寛平九年(897年)には正一位を授けられ、また延喜式内の名神大社として高い地位にありました。
古代から筑紫の国魂と仰がれ、筑後一円はもとより、肥前にも有明海に近い地域を中心に篤い信仰圏が見られ、厄年の厄ばらい・厄除け開運・延命長寿・現代では交通安全のご利益でも名高い神社です。
主祭神は、古事記や日本書記に登場しない「高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)」で、この神様は神功皇后の側近だった武内宿禰や、海人族の阿曇磯良だという説があります。
現在の本殿、幣殿、拝殿は、久留米藩主有馬頼利(3代)の建立で、江戸初期の権現造で、神社建築としては九州最大規模を誇る国の重要文化財となっています。
万治3年(1660年)に本殿が、寛文元年(1661年)に幣殿・拝殿が完成しました。
社宝に「紙本墨書平家物語」(重要文化財)、「絹本著色高良大社縁起」(県文化財)などがあり、山中の孟宗金明竹(国の天然記念物)も貴重な文化財として保存されています。
孟宗竹の金明竹は全国にありますが、孟宗竹はここを含めて全国で4ヶ所だけと非常に珍しく、国の天然記念物に指定されています。
不思議なことに、高良大社と、日吉神社の旧鎮座地であり、現在篠山神社が鎮座する久留米城跡、合川町の筑後国府跡とは一直線になっており、夏至の日の入りと冬至の日の出の直線と重なり、「光の道」として神秘的な現象を見ることができます。
その他の重要な寺社
久留米市には、上記以外にも多くの重要な寺社があります。
善導寺は浄土宗の大本山であり、国の重要文化財に指定された建造物が残る貴重な寺院です。
久留米市の歴史的建造物として、その建築様式や仏教美術の観点からも高い価値を持っています。
北野天満宮は、学問の神様・菅原道真公を祀る神社であり、受験シーズンには多くの学生が合格祈願に訪れます。
久留米市内の学生たちにとって、学業成就の聖地として親しまれています。
これらの神社仏閣は、久留米市の歴史と文化を今に伝える大切な存在となっています。
久留米藩の歴史、平家の悲劇、修行道場としての伝統、そして市民の日常的な信仰生活まで、様々な側面から久留米市の豊かな精神文化を物語っています。
四季折々の自然と調和した境内は、参拝者に心の安らぎを与え、久留米市民の心の拠り所として、また観光資源としても重要な役割を果たし続けています。
10.久留米シティプラザ
久留米シティプラザは、2016年4月に開館した久留米市の文化芸術の中心拠点として、市民や観光客に愛される複合文化施設となっています。
1969年(昭和44年)に完成した久留米市民会館は建物が老朽化し、久留米市は新たなる文化施設を計画した。
2016年(平成28年)4月、久留米井筒屋・六角堂広場跡地に久留米シティプラザが落成しました。
施設の特徴と魅力
〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1に位置する久留米シティプラザは、設計は建築家の香山壽夫であることで知られ、久留米の伝統と現代が見事に融合した建築美を誇ります。
世界的に著名な建築家による設計は、単なる文化施設を超えた芸術作品としての価値も持ち合わせています。
施設内には多彩な空間が配置されており、それぞれが異なる文化活動に対応できる設計となっています。
メインとなる「ザ・グランドホール」は、座席番号が見にくい方は、↑こちらのリンクから見られますよ。
4階席は縦4A~4E列までの5列、横は下手1番~上手42番まで座席がありますという大規模な劇場空間を有し、本格的な舞台芸術の上演に適した環境を提供しています。
中ホール「Cボックス」は、より親密な空間での公演に適しており、久留米座という能舞台も備えています。
ちょうせい。
和室8畳3室。
茶華道、書道など。
2024年に第50期天元戦第3局(一力遼天元vs芝野虎丸九段)の対局場となるなど、日本の伝統文化の継承にも重要な役割を果たしています。
多彩な公演プログラム
久留米シティプラザでは、年間を通じて幅広いジャンルの公演が開催されています。
727(土) Shizuka Kudo 「明鏡止水~piece of my heart~」 Concert Tour 2024 [会場]ザ・グランドホール 時代を彩るヒット曲から最新曲まで、甘く伸びやかな歌声がザ・グランドホールに響きわたるなど、国内外の著名アーティストによる公演が定期的に行われています。
演劇分野では、921(土) 22(日) PARCO PRODUCE 2024 破門フェデリコ~くたばれ!十字軍~ 実の息子も敵に回し、全世界を敵に回しても、 前人未到の道に進もうとした皇帝フェデリコの物語 佐々木蔵之介×上田竜也で中世ヨーロッパの壮大な物語が動き出す!といった話題作が上演されています。
地元久留米市出身のアーティストも積極的に起用されており、622(土)23(日) PARCO PRODUCE 2024『ハムレットQ1』 [会場]ザ・グランドホール 久留米市出身の吉田羊がシティプラザの舞台に初登場など、地域とのつながりを大切にした企画も実施されています。
アクセスと利便性
久留米シティプラザへのアクセスは非常に便利で、JR久留米駅から 【路線バス】約10分「六ツ門・シティプラザ前」下車すぐ 【徒歩】約20分、西鉄久留米駅からも徒歩約10分という好立地にあります。
施設内には地下駐車場も完備されており、駐車料金:最初の1時間は200円、以後30分ごとに100円 (4時間以上12時間以内800円、12時間以降は1時間ごとに100円)という料金設定で、車での来場にも対応しています。
久留米シティプラザをご利用の方で、身体障害者手帳・ 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、利用した時間分、駐車料金を減免いたしますという配慮もなされています。
開館時間と施設利用
開館時間:8時30分~22時00分(貸出は9時~22時) 総合受付:10時~19時 六角堂広場・地下駐車場:7時30分~22時30分(開放時間)(貸出は9時~22時) カタチの森:9時~19時となっており、朝から夜まで幅広い時間帯で利用可能となっています。
休館日は年末年始 12月29日~1月3日 (注意)施設の保守点検等を行うため、臨時休館日を設けることがありますと設定されており、年間を通じてほぼ利用できる体制が整っています。
久留米市の文化的魅力
久留米シティプラザがある久留米市は、文化施設が充実した都市として知られています。
2016年11月19日(土曜)、開館。
昭和31年に開館した石橋美術館を前身とし、「とき・ひと・美を結ぶ美術館」として平成28年11月にオープン。
久留米や九州ゆかりの近代洋画を収蔵し、多彩な展覧会が魅力ですという久留米市美術館も近隣にあり、石橋文化センター内に位置しています。
美術館では、異端の奇才ビアズリー展 令和7年5月24日(土曜日)から8月31日(日曜日)まで 橋口五葉のデザイン世界 令和7年9月13日(土曜日)から10月26日(日曜日)までなど、年間を通じて魅力的な展覧会が開催されています。
グルメの街・久留米
文化施設巡りの合間には、久留米市の豊かな食文化も楽しめます。
久留米市は、とんこつラーメン発祥の地として全国的に有名ですが、それだけでなく多彩なグルメが楽しめる街でもあります。
和の趣を感じる空間には、テーブル席や座敷席が全24席用意されています。
美しい庭園をめながら食事を楽しめるとのことという落ち着いた雰囲気のレストランから、久留米市田主丸町石垣にある「ダルマサーガラ」は、ランチで本格的なインド料理を堪能できるお店のような国際色豊かな料理まで、幅広い選択肢があります。
特に注目すべきは、ここは久留米市にある 『馳走おがた』 ずっと前から行きたかったとこにやっと
久留米市の産業と経済の現状
久留米市は福岡県南部に位置する人口約30万人の中核都市で、筑後川の恵みを受けた豊かな自然環境と、多様な産業基盤を併せ持つ地域として発展を続けています。
江戸時代には久留米有馬藩の城下町として栄え、現代においても九州の交通の要衝として重要な役割を果たしているのが特徴的でしょう。
久留米市の産業構造において最も象徴的な存在が、世界的タイヤメーカーであるブリヂストンの存在です。
1931年3月に操業を開始した久留米工場は、ブリヂストンの国内で最初のタイヤ工場として、現在でもブリヂストングループを支える生産拠点に位置付けられています。
同工場は小型トラック用タイヤをはじめ、航空機用、モータースポーツ用等の各種タイヤを幅広く生産し、タイヤの骨格となるナイロンコードを撚って織るコード工場も備えており、国内外工場へ供給しています。
ゴム産業の集積は久留米市の産業発展の礎となり、関連企業や協力工場が市内に多数立地することで、地域経済に大きな波及効果をもたらしています。
タイヤ製造に関わる機械設備メーカーや部品供給企業なども含めると、その経済効果は計り知れません。
医療産業の面では、久留米大学病院が特定機能病院として急性期をはじめとした幅広い医療に取り組み、地域がん診療連携拠点病院、福岡県総合周産期母子医療センター、高度救命救急センター、災害拠点病院など、多くの役割を担っています。
同病院は病床数1018床(一般965床、精神53床)を有し、常勤換算で59086名の医師が勤務する大規模医療機関となっています。
この久留米大学病院を中心とした医療クラスターは、医療従事者の雇用創出だけでなく、医療機器関連産業や医薬品産業、さらには医療系の研究開発機関の集積にもつながっています。
医学部を有する久留米大学の存在により、医療人材の育成から最先端医療の研究開発まで、幅広い医療産業の発展を支える基盤が整っているといえるでしょう。
自動車関連産業においては、ダイハツ九州の存在が大きな影響力を持っています。
久留米工場は福岡県久留米市田主丸町に立地し、就業者数500名(2023年1月現在)で、生産能力216,000基/年のエンジン製造を行っています。
2008年(平成20年)に軽自動車エンジンの生産を開始した同工場は、地域に密着した企業を目指しており、エンジンの鋳造から加工、組立、品質検査まで一貫した生産体制を構築しています。
大分県中津市にある本社・工場では、就業者数4,000名(2023年1月現在)、生産能力480,000台/年の規模で、ハイゼット、ミライース、ウェイクなどの軽自動車を生産しており、久留米工場で製造されたエンジンが供給される仕組みとなっています。
自動車産業は裾野が広く、部品メーカーや物流企業など、多くの関連企業が久留米市内に立地することで、地域経済の活性化に貢献しています。
食品加工業も久留米市の重要な産業の一つで、筑後川流域の豊かな農産物を活用した食品製造業が発展しています。
農業者が主体的に自ら生産した農産物を活用して、加工や商品開発を行い、流通や販売を行う6次産業化の取り組みも活発で、農業者の所得向上だけでなく、関連企業、地域の活性化にも繋がっています。
商業面では、ゆめタウン久留米をはじめとする大型商業施設が立地し、久留米シティプラザ周辺は文化と商業の中心地として賑わいを見せています。
地場産くるめ(久留米地域地場産業振興センター)では、筑後の伝統工芸品や物産が地域産業、生産組合の24業者から出品、展示されており、久留米絣関係の資料室や郷土の土産品コーナーが人気を集めています。
久留米市の産業振興政策も充実しており、情報通信関連企業等に対する産業振興奨励金制度では、常時従業者20人以上(中小企業者等は5人以上)かつ市民の新規雇用者が5人以上の企業に対し、業務施設の年間賃借料及び年間共益費の50%(3年度間の限度額1,500万円)や、事業の用に供する設備機器・備品の取得費及び事業所設置工事費等の50%(3年度間の限度額2,000万円)を支援しています。
創業支援の面でも、久留米市内の中小製造業者が行う「ものづくり」分野の新製品・新技術の研究開発に対し、経費の一部を支援する制度があり、育成支援型では対象経費の2/3以内で上限110万円、実用化支援型では対象経費の2/3以内で上限330万円の支援を行っています。
交通インフラの充実も久留米市の産業発展を支える重要な要素となっています。
九州自動車道や国道3号線をはじめとする広域幹線道路、市内全域を網羅する路線バス網、JRは九州新幹線と鹿児島本線、久大本線、西鉄は天神大牟田線などの鉄道が縦横に走っていることで、物流や人の移動が円滑に行われ、企業活動を支えています。
このように久留米市は、伝統的なゴム産業を基盤としながら、医療、自動車、食品加工など多様な産業が集積し、それぞれが相互に連携しながら地域経済を支えています。
産業振興政策の充実や交通インフラの整備により、今後も持続的な経済成長が期待される地域といえるでしょう。
久留米市の主要産業
久留米市の経済を支える主要産業について、より詳しくご説明いたします。
ゴム産業 – 世界的企業ブリヂストンの創業地
久留米市のゴム産業の歴史は、1906年3月に17歳で家業の仕立物業を引き継いだ石橋正二郎氏が、足袋の専業を始めたことから始まりました。
その後、地下足袋やゴム靴の製造を経て、1931年3月1日に石橋正二郎によって福岡県の久留米市で「ブリッヂストンタイヤ株式会社」が創業されました。
社名の由来は興味深く、創業者の姓”石橋”を英訳し、STONE BRIDGEとなるが、これでは語呂が悪いので逆さにしてBRIDGESTONEと決定されたのです。
当初から海外進出を視野に入れていたことがわかります。
久留米工場は、ブリヂストンの国内で最初のタイヤ工場として、タイヤの国産化を使命に1931年3月、操業を開始しました。
現在もマザープラントとして、小型トラック用タイヤをはじめ、航空機用、モータースポーツ用等の各種タイヤを幅広く生産しており、海外工場などから多くのスタッフが久留米工場へ研修に来るなど、技術の中心地となっています。
創業者の地域貢献への思いも強く、石橋文化センターの建設寄贈(1956)、ブリヂストン美術館(現・アーティゾン美術館)の創設(1952)など、文化事業にも力を注いできました。
自動車関連産業 – ダイハツ九州の生産拠点
ダイハツ九州株式会社久留米工場は、福岡県久留米市田主丸町吉本1番地に立地しています。
2008年(平成20年)に久留米市田主丸町にて軽自動車エンジンの生産を開始した工場で、軽自動車のエンジン生産に最適な『SSC(シンプル・スリム・コンパクト)』な工場とし、スモールカー分野で世界No1のクルマづくりをめざすエンジン工場として稼働しています。
鋳造で高温で溶けたアルミを型に流し込む方法と、圧縮して押し込む2つの方法でエンジンの部品を製造し、機械加工では、ミクロンサイズ(0001mm単位)の精度で加工を行うなど、高度な技術力を有しています。
地域との連携も重視し、工場見学を通じて地域社会との交流も積極的に行っています。
医療・バイオ産業 – 高度医療都市としての発展
人口当たりの医師数は、全国トップレベルであり、久留米大学医学部をはじめPET等の最先端医療設備を持つ施設が集積した高度医療都市となっています。
久留米大学病院や聖マリア病院といった大規模医療機関が、地域医療の中核を担っています。
バイオ産業については、従来の製造業一辺倒からの脱却を図るために、バイオ産業の集積をめざす「福岡バイオバレープロジェクト」のもと福岡県と共同でバイオ関連産業の育成・振興が推進されています。
株式会社久留米リサーチ・パーク内に、平成16年4月に福岡バイオインキュベーションセンター、平成19年4月に福岡バイオファクトリー、令和3年4月に福岡バイオイノベーションセンターを建設し、バイオ産業の拠点化を推進しています。
これらの施設では、バイオベンチャー企業の育成や研究開発支援が行われており、産学官連携による新産業創出が進められています。
農業 – 全国有数の植木・苗木産地
植木の日本四大生産地の1つである、福岡県久留米市として知られ、福岡県久留米市とその近郊は日本でも有数の植木や果樹苗の産地です。
その歴史は300年以上に及び、久留米市の緑化産業は、江戸時代元禄年間に始まり、300年を超える伝統あるもので、全国に誇れる一大産地となっています。
久留米の植木は豊かな土壌と気象条件に恵まれ、「つつじ」を中心に古くは江戸時代より発展し続けてきました。
特に田主丸地域は植木・苗木生産の中心地として、当地で生産される植木や果樹苗は全国に販売されるとともに海外へも輸出されています。
毎年開催される久留米植木まつりでは、久留米市の植木苗木の業者が一堂に会し、1000種類10万本の展示即売が行われ、全国から多くの来場者を集めています。
伝統産業 – 久留米絣の継承
久留米絣は、200年以上の歴史を持つ伝統的な織物で、国の重要無形文化財に指定されています。
藍染めの深い色合いと精緻な絣模様が特徴で、現在も職人たちによって技術が受け継がれています。
伝統を守りながらも、現代的なデザインを取り入れた製品開発も進められており、地域の文化的アイデンティティを形成する重要な産業となっています。
このように久留米市は、世界的企業から伝統産業まで、多様な産業が共存し、それぞれが地域経済を支える重要な柱となっています。
特に、ゴム産業で培われた技術力と、医療・バイオ分野での先進的な取り組み、そして300年以上の歴史を持つ植木産業など、新旧の産業がバランスよく発展している点が久留米市経済の大きな特徴といえるでしょう。
商業施設と企業の動向
久留米市の商業施設は、地域経済の発展において極めて重要な役割を果たしており、伝統的な百貨店から最新の大型ショッピングセンターまで、多様な商業形態が共存しているのが特徴といえるでしょう。
市内最大級の商業施設である「ゆめタウン久留米」は、約150店舗が入居し、年間1,000万人以上が訪れる集客力を誇り、食品売場は9:30~21:00、専門店は10:00~21:00まで営業しており、地域住民の生活を支える中核施設となっています。
西鉄久留米駅周辺では、2024年に大きな変化が訪れました。
西鉄久留米駅ビルが2年間のリニューアル工事を経て、商業施設「エマックス・クルメ」から「レイリア久留米」として2024年10月12日にグランドオープンし、60店舗体制で年間売上約30億円を記録しています。
この施設は”行き交う人がちょっと一息つける、街の中のオアシス空間”をリニューアルコンセプトに掲げ、駅ビルとしての利便性を最大限に活かした商業展開を行っています。
また、岩田屋久留米店や久留米シティプラザなども立地し、中心市街地の活性化に貢献しているのが現状でしょう。
特に西鉄久留米駅ビルには久留米バスセンターも併設され、1階から4階まで多様な店舗が入居し、交通結節点としての機能も果たしています。
企業動向としては、ブリヂストンの創業地として知られる久留米市には、1931年3月に操業を開始した同社の久留米工場が稼働しており、現在も約3,000人の雇用を生み出しています。
久留米工場は筑後川河畔に立地し、環境にやさしい工場づくりを推進しながら、地域社会に溶け込んだ工場運営に取り組んでいます。
近年では、IT関連企業の進出も目立ち、久留米リサーチ・パークには久留米市百年公園敷地内に賃貸オフィスや研究開発スペースを建設し、バイオベンチャーや研究機関などのバイオ関連産業の集積を目指す「福岡バイオバレープロジェクト」を推進しており、約40社が入居しています。
2024年度には「くるめDX講座(ITブートキャンプ)」を開催し、産学官テクノ交流会も実施するなど、技術革新の拠点としても機能しています。
「このまま企業誘致が進めば、若者の流出も防げるかもしれない…」と期待する声も聞かれます。
実際に、JR久留米駅前では第二街区市街地再開発事業が進行中で、2027年春に地上131mの高さとなる久留米市内最高層のタワーマンションと商業施設の複合ビルが完成予定となっており、新たな都市開発が進んでいます。
商業施設の新規出店も続いており、2023年には「コストコ久留米倉庫店」の出店計画が発表されました。
しかし実際には、2024年11月21日に小郡市に「コストコ小郡倉庫店」が福岡県内3店目としてオープンし、久留米市近郊の商業環境が大きく変化しています。
小郡市の新店舗は敷地面積約6万8,800㎡、売場面積1万㎡で、900台以上の駐車場を設置し、350人以上の従業員が雇用されるという大規模な施設となっています。
一方、久留米市内では2024年12月31日に「コストコくるめ再販店」が上津町にオープンし、会員証不要、24時間営業の無人販売でコストコ商品を購入できる新しい形態の店舗も登場しました。
地元商店街との共存を図りながら、以下のような取り組みが進められています。
– 商店街活性化事業 空き店舗を活用した新規創業者への支援制度を実施し、補助金交付により店舗の1年以上の良好な営業継続を支援。
年間約20件の新規出店を実現しています。
– デジタル化推進 キャッシュレス決済の導入支援により、商店街の利便性向上を図っています。
特に2024年度のくるめDX講座では、ITブートキャンプを開催し、地域のデジタル化を推進しています。
久留米市の商業施設と企業は、伝統と革新のバランスを保ちながら、地域経済の発展に寄与し続けているといえるでしょう。
特に、駅ビルのリニューアルや新たな商業施設の進出、IT企業の集積など、多様な産業が融合することで、持続可能な地域経済の構築を目指しています。
久留米市の特産品と郷土料理
久留米市の特産品として真っ先に挙げられるのは、全国的に有名な久留米絣です。
この伝統工芸品は200年以上の歴史を持ち、藍染めの深い色合いと精緻な絣模様が特徴となっています。
現在でも職人の手によって一つひとつ丁寧に作られており、着物や小物として多くの人に愛されているのです。
食の分野では、久留米ラーメンが代表的な郷土料理として知られています。
豚骨をじっくり煮込んだ濃厚なスープと、中太のストレート麺が絶妙にマッチ。
「これぞ本場の味!」と感動する観光客も多いでしょう。
市内には老舗から新進気鋭の店まで約200軒のラーメン店が軒を連ねており、食べ比べを楽しむのもおすすめです。
農産物では、筑後平野の豊かな土壌で育った米や野菜が有名。
特に田主丸地区で栽培される巨峰やシャインマスカットは、糖度が高く果汁たっぷりで人気を集めています。
その他の特産品として注目したいのが以下の品々。
– 久留米つばき油 椿の実から採れる純度の高い油で、食用や化粧品として重宝されています。
– 筑後うどん コシのある麺と甘めのつゆが特徴的な地元民に愛される一品。
– 城島瓦せんべい 瓦の形をした香ばしいせんべいで、お土産として人気があります。
これらの特産品は、久留米市の風土と歴史が育んだ貴重な財産といえるでしょう。
久留米市に関するよくある質問
久留米市への観光を計画している方にとって、事前に知っておきたい情報は数多くあるでしょう。
ここでは、久留米市に関して多くの方が疑問に思う内容について、わかりやすく解説していきます。
観光地選びから交通アクセス、地元のイベント情報まで、旅行計画を立てる際に役立つ情報は実に幅広いものです。
特に初めて久留米市を訪れる方にとっては、効率的に観光を楽しむためのポイントを押さえておくことが重要になります。
また、久留米市の教育環境について知りたい方も多く、移住や長期滞在を検討している方からの質問も寄せられています。
例えば、久留米市の代表的なイベントである「水の祭典久留米まつり」の開催時期や、JR久留米駅・西鉄久留米駅からの観光地へのアクセス方法、久留米大学をはじめとする教育機関の特色など、実際に訪れる前に知っておくと便利な情報がたくさんあります。
これらの疑問に対する答えを事前に把握しておけば、より充実した久留米観光を楽しむことができるはずです。
以下で詳しく解説していきます。
久留米市の魅力的な観光スポット
久留米市は、九州でも有数の食文化が息づく場所であり、一年を通して「花」と「フルーツ」を楽しむことができる観光都市となっています。
歴史的な名所と現代的な文化施設が調和よく配置されていることが、久留米観光の大きな特徴といえるでしょう。
高良山に鎮座する高良大社は、筑後国一の宮として知られ、1600年以上の歴史を持つ重要な社であり、九州最大級の社殿は国の重要文化財に指定されています。
境内へと続く131段の石段からは久留米市内を一望でき、時期によっては石段の中心に夕日が落ちる「光の道」の絶景を見ることも可能となっています。
石橋文化センターは四季折々の美しい庭園と充実した文化施設で訪問者を魅了し、4月下旬から5月上旬には約400種2600株のバラが咲き誇る様子は圧巻という評判を得ています。
久留米市美術館は、ブリヂストンの創業者石橋正二郎が自身の出身地である久留米市に寄贈した「石橋美術館」が前身で、2016年に改装され新たに開館しました。
家族連れには、久留米市鳥類センターは約90羽ものクジャクを主体に、タンチョウやフラミンゴなど約80種420点もの鳥類が見られる全国でも珍しい鳥類専門の動物園として人気があります。
観覧車やメリーゴーランドなどの遊具が揃ったプレイランドも併設され、動物観察と遊園地の両方を楽しめる施設となっています。
久留米市の中心部にあり、地下1260mまで掘削する源泉掛け流しの温泉施設「源泉掛け流し温泉 久留米 游心の湯」では、Ph97のとろみのある温泉がたっぷり浴槽に注がれ、日頃の疲れを癒すことができます。
男女別の大浴場には、高濃度炭酸泉風呂、つぼ湯、座り湯、フィンランド式ロウリュサウナも完備されています。
久留米市の豊かな食文化
久留米市は、とんこつラーメン発祥の地とも言われ、白濁した濃厚スープの「久留米ラーメン」を筆頭に、個性豊かな「久留米餃子」や鶏以外にも幅広い食材を串で楽しむ「久留米焼きとり」など、屋台文化により広がった多彩なご当地グルメが楽しめます。
かつて筑後川は天然うなぎの好漁場だったことから、うなぎの名店も多数あり、流域の肥沃な大地は小麦の二毛作が盛んで、栽培農家を中心にやわらかくモチモチとした筑後うどんを日常的に食べる文化も根付きました。
豊かな自然に恵まれた耳納連山の麓や筑後川流域を中心に、15もの酒蔵が点在する名醸地としても知られ、フルーツの栽培も盛んで、巨峰100%醸造のワインをはじめ、ブルーベリーやイチゴを使ったオリジナルのフルーツワインも造られています。
柿狩り、シャインマスカット狩り、梨狩りなど、季節ごとのフルーツ狩りも楽しめ、ぶどう、いちご、柿、梨、イチジクなどの果樹園も多数あり、採れたてのフレッシュな果物を味わえるフルーツ狩りができる施設も多く、四季折々の風景や味覚を存分に堪能することができます。
水の祭典久留米まつりの詳細情報
久留米が一番燃え上がり、熱くなるサマーフェスティバル「水の祭典久留米まつり」は、令和7年7月20日(日曜日)の「子ども太鼓フェスティバル」で幕を開け、8月3日(日曜日)は「前夜祭」、8月4日(月曜日)は「本祭」が開催されます。
前夜祭(8月3日)は久留米シティプラザ六角堂広場で、よさこいなどのステージイベントやお楽しみ抽選会などが行われ、本祭(8月4日)は久留米市明治通りで、パワーストリート、太鼓響演会、一万人のそろばん総踊り、本祭ファイナルなどが催されます。
本祭では、13時00分~16時30分にパワーストリート、16時30分~17時30分に太鼓響演会、18時30分~20時20分に一万人のそろばん総踊り、20時30分~20時40分に「音と水の競演・ウォーターイルミネーション」が行われる本祭ファイナルという充実したプログラムが組まれています。
熱中症対策として、福岡県に「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、または久留米市の暑さ指数(WBGT)が35以上と予想された場合は、日中のプログラムを中止し、一万人のそろばん総踊りからの開催となります。
「久留米シティプラザ2階展示室2」を救護所/休憩スペースとして開放するなど、参加者の安全にも配慮されています。
久留米市内の交通アクセス
久留米市の代表駅であるJR久留米駅は、繁華街などの市街地からやや西に位置し、東に約2kmほど離れた西鉄久留米駅と区別するため、バス停留所の名称や地元での通称は「JR久留米駅」などとなっています。
西鉄久留米駅から久留米シティプラザまでは、タクシー約4分、路線バス約5分、徒歩約10分、JR久留米駅から久留米シティプラザまでは、タクシー約7分、路線バス約10分、徒歩約20分でアクセス可能となっています。
福岡空港から久留米市へは、福岡市営地下鉄空港線でJR博多駅まで約6分、JR博多駅から九州新幹線で約17分またはJR鹿児島本線快速約35分でJR久留米駅に到着します。
また、福岡市営地下鉄空港線で西鉄福岡(天神)駅まで約11分、西鉄天神大牟田線特急で約32分で西鉄久留米駅に到着という複数のルートが利用できます。
JR久留米駅のまちなか口ロータリーにバスのりばが設けられており、西鉄バスと堀川バスが利用可能で、当駅から西鉄久留米駅までは所要時間10分程度で運賃は170円という手頃な料金で移動できます。
久留米大学の教育環境と特色
久留米大学は九州医学専門学校を前身として、6学部(医学部・商学部・法学部・文学部・経済学部・人間健康学部)と5研究科を有する私立総合大学として発展してきました。
まもなく設立100周年を迎え、ブリヂストンの創業者石橋正二郎氏も創立に尽力した、歴史ある大学という背景を持っています。
創立90有余年の歴史の中で築いてきた地域との連携を生かし、文系学部では、地元の酒造や菓子店やお茶農園等と連携しながら、一連の商品開発に参加し、社会と関わりながら自己を磨くとともに、地域の発展に役立つという意識を育んでいます。
「THE世界大学ランキング2024」において私立大学で全国5位(同位)という高い評価を受けており、これまでに1万人以上の医師を輩出し、久留米には病院や診療所も多く、「医者のまち」とも呼ばれています。
医学部看護学科サークル「はなみずき」は、地域の障がい者支援活動や筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんへの支援を積極的に行っており、「サークル・久留米大学BBS会」は、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指して、児童擁護施設訪問などのボランティア活動を10年以上行ってきました。
この活動が評価され、法務大臣表彰を受けるなど、学生の社会貢献活動も活発に行われています。
久留米大学は教員と学生の「心の距離」が近く、日々の学びや就活も親身になって全力サポートし、毎年90%以上の就職決定率を誇ります。
学びの本質は受験勉強ではなく、知らなかったことを知ることによって視野を広げることであり、久留米大学は、学生の皆さんの本質的な学びや成長を支える「入ってから、伸びる大学」という教育理念を掲げています。
久留米市の有名なイベントは?
久留米市では年間を通じて多彩なイベントが開催され、多くの観光客や地元の方々で賑わいます。
特に有名なのは、毎年5月3日から5日にかけて開催される「久留米つつじまつり」でしょう。
久留米百年公園では約10万本のつつじが咲き誇り、「まるで花の絨毯のようだ」と感動する来場者も少なくありません。
8月上旬の「筑後川花火大会」は、西日本最大級の規模を誇る花火大会として知られています。
約1万8000発の花火が夜空を彩り、筑後川の水面に映る光景は圧巻。
毎年45万人以上の観客が訪れる、久留米市最大の夏の風物詩となっています。
秋には「久留米焼きとり日本一フェスタ」が開催され、全国から焼きとり店が集結。
久留米の焼きとり文化を全国に発信する重要なイベントとして定着しました。
その他にも注目すべきイベントがあります。
– 水の祭典久留米まつり(7月下旬) パレードや総踊りなど、市民参加型の夏祭りとして親しまれています。
– 久留米たまがる大道芸(11月) 国内外のパフォーマーが街中で大道芸を披露する秋のイベントです。
– 城島酒蔵びらき(2月) 地元の酒蔵が一斉に開放され、新酒の試飲や販売が楽しめます。
これらのイベントは久留米市の魅力を存分に体感できる絶好の機会となっています。
久留米市の交通アクセスは?
久留米市は九州の交通の要衝として、鉄道・高速道路・空港からのアクセスが抜群に優れた都市となっています。
その利便性の高さと充実した交通網について、詳しくご紹介しましょう。
鉄道アクセスの充実度
久留米市には2つの主要駅があり、それぞれが異なる役割を担っています。
JR久留米駅は九州新幹線の停車駅として、博多駅から新幹線なら約15分という驚異的な速さでアクセス可能。
在来線の鹿児島本線でも約35分と、通勤・通学にも便利な距離感となっています。
一方、西鉄久留米駅は市内最大の繁華街に位置し、福岡天神から特急で約30分でアクセスできる好立地。
西鉄天神大牟田線は福岡都市圏と筑後地域を結ぶ重要な路線として機能しており、買い物や観光の拠点として多くの人々に利用されています。
運行本数についても心配は無用で、JR久留米駅では朝6時台から夜まで、1時間に3~4本程度の列車が運行されており、日中も頻繁に列車が発着しています。
通勤ラッシュ時にはさらに本数が増え、利用者のニーズに応えた運行体制が整備されているのが特徴的。
高速道路網の結節点
車でのアクセスも非常に優れており、九州自動車道の久留米インターチェンジは市内中心部から約10分という近さにあります。
このインターチェンジは九州自動車道と大分自動車道の分岐点となっており、九州各地への移動の要所として機能しています。
福岡空港からは高速道路を利用して約40分、佐賀空港からも約50分でアクセス可能となっており、空の玄関口からの移動もスムーズ。
ビジネスや観光で九州を訪れる際の拠点として、理想的な立地条件を備えています。
市内交通の利便性
久留米市内の移動には西鉄バスが大きな役割を果たしており、主要観光地や商業施設を結ぶ路線網が張り巡らされています。
西鉄久留米駅からは、JR久留米駅・高専前・大学病院方面など、市内各地への路線バスが運行されており、車を持たない観光客でも市内観光を楽しむことができる環境が整っています。
さらに公共交通の利用が不便な地域には「よりみちバス」と「コミュニティタクシー」という生活支援交通が導入されており、きめ細やかな交通サービスが提供されています。
久留米広域連携中枢都市圏では、圏域内の公共交通情報をまとめた「公共交通マップ」を作成し、利用者の利便性向上にも取り組んでいます。
観光拠点としての魅力
久留米市は交通アクセスの良さを活かし、九州一の大河、筑後川と筑後平野、耳納連山に囲まれる自然豊かな観光都市として発展してきました。
高良大社は1600年以上の歴史を誇る由緒正しい神社で、九州最大級の社殿は国の重要文化財に指定されており、歴史的価値の高い観光スポットとなっています。
また、石橋文化センターは四季折々の美しい庭園と充実した文化施設で訪問者を魅了し、久留米市鳥類センターは約80種420点もの鳥類が見られる全国でも珍しい鳥類専門の動物園として、ファミリー層に人気を集めています。
グルメの面でもとんこつラーメン発祥の地として知られ、久留米ラーメンを筆頭に久留米餃子や久留米焼きとりなど、屋台文化により広がった多彩なご当地グルメが楽しめる魅力的な都市。
15もの酒蔵が点在する名醸地としても有名で、食文化の豊かさも久留米市の大きな魅力となっています。
このように久留米市は、九州新幹線の停車駅として広域からのアクセスが容易であり、市内の交通網も充実した、まさに九州観光の理想的な拠点都市といえるでしょう。
歴史・文化・自然・グルメと多彩な魅力を持つ久留米市は、交通の利便性を最大限に活かした観光都市として、今後もさらなる発展が期待されています。
久留米市の教育機関について知りたい
久留米市の教育環境は、幼児期から高等教育まで、実に多層的で充実した体制が整備されています。
基礎教育の充実した基盤
久留米市では、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、授業の終了後に学童保育施設を利用して適切な遊びや生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図っています。
市内には公立小学校46校、中学校17校が設置され、地域の子どもたちの学びを支える基盤となっています。
特筆すべきは、久留米市教育委員会が令和5年2月に久留米市立小学校小規模化対応方針の改正を行い、児童数の推計や学校施設の状況について、広く市民との情報共有に努めている点でしょう。
少子化による学校の小規模化という課題に対し、地域と連携しながら対応を進めているのが現状です。
医療系教育の拠点として
久留米市の高等教育機関で最も存在感を示すのが、久留米大学医学部です。
医学部は90有余年の歴史を背景に、最高水準のスタッフと最新鋭の設備により、現代医学の最先端教育と人間形成を実践しており、医学科は「時代や社会、そして地域の多様なニーズに対応できる実践的でヒューマニズムに富む医師を育成する」を教育目的としています。
久留米大学医学部地域医療連携講座では、久留米大学特別枠・福岡県特別枠の制度を設け、地域枠の設置背景や義務内容、卒業後のキャリアについて詳しく説明していることからも、地域医療への貢献を重視していることがうかがえます。
久留米大学は前身である九州医学専門学校の創立以来、全国最多とも言われる病院経営者、診療所開設者を輩出し地域医療を支えてきました。
工学系人材育成と産学連携
久留米工業大学は、地域の産業発展に欠かせない存在となっています。
同大学では「地域課題解決型AI教育プログラム」が日本工学教育協会賞の工学教育賞に輝き、九州工学教育協会賞とのダブル受賞を果たしています。
令和6年度には農水省採択事業「スマート農業技術の開発・供給」のキックオフ会議が開催され、久留米工業大学はAI技術を用いた果実の画像認識精度の研究を担当しているなど、最新技術を活用した地域課題の解決に積極的に取り組んでいます。
自動車・半導体の人材育成に関する産学官連携コンソーシアム協定を締結するなど、地元企業との連携も活発に展開されています。
専門職教育の多様性
医療・福祉系の専門教育も充実しており、久留米リハビリテーション学院では理学療法士と作業療法士のリハビリ学科に特化し、国家資格の試験対策と就職サポートが万全の体制を整えています。
同学院では、医療法人立の強みを活かした現場直結型の実習体制や、「KRi AI学習支援システム」による国家試験対策で、全国平均を大きく上回る合格率を誇っています。
また、久留米高等技術専門校では建築科、介護サービス科、ものづくり×プログラム科、自動車整備科などの訓練科目を設置し、実践的な技術習得の場を提供しています。
子育て支援体制の充実
働く保護者への支援体制も整備されており、市内44校区に学童保育所が開設され、開所時間は18時まで、希望者には平日のみ19時までの延長保育も行っています。
放課後や夏休みなどの長期休業中には、週1回程度、市内の大学生を学習ボランティアとして一部の市立小学校、中学校へ派遣し、子どもたちのやる気を育て、学習の習慣づけのお手伝いをしています。
学童保育所の基本利用料は、月曜日から金曜日までの利用で月額5,000円、土曜日も利用される場合は月額6,500円で、生活保護受給世帯や就学援助認定世帯には減額制度が設けられているなど、経済的な配慮も行われています。
教育都市としての総合力
このように久留米市は、基礎教育から専門教育、そして生涯学習まで、あらゆる世代の学びを支える教育インフラが整備されています。
特に医療系・工学系の高等教育機関が地域産業と密接に連携し、実践的な人材育成を行っている点が大きな特徴といえるでしょう。
図書館や文化施設も教育活動に積極的に活用され、学校教育の枠を超えた学びの機会が提供されています。
久留米市は単なる教育施設の集積地ではなく、地域全体で次世代を育てる「教育都市」として、その役割を果たし続けているのです。
まとめ:久留米市の魅力的な観光スポットを巡ろう
今回は、久留米市の観光を計画している方に向けて、- 歴史ある寺社仏閣の見どころ- 自然豊かな公園や庭園の魅力- 地元グルメと観光を組み合わせた楽しみ方上記について、解説してきました。
久留米市には、水天宮や成田山久留米分院などの由緒ある寺社から、石橋文化センターの美しい庭園まで、多彩な観光スポットが点在しています。
歴史と文化、そして豊かな自然が調和した街の魅力を、ぜひ実際に訪れて体感してみてはいかがでしょうか。
観光地を巡りながら、久留米ラーメンや焼き鳥といった名物グルメも堪能できるのが、この街の大きな魅力です。
これまで福岡観光といえば博多や天神を中心に回っていた方も、久留米市まで足を延ばすことで、新たな九州の魅力を発見できるはずです。
筆者が紹介した観光スポットは、どれも久留米市ならではの個性が光る場所ばかり。
四季折々の風景を楽しめる久留米市は、何度訪れても新しい発見があることでしょう。
次の休日には、ぜひ久留米市の観光スポットを巡って、思い出に残る素敵な一日を過ごしてくださいね。









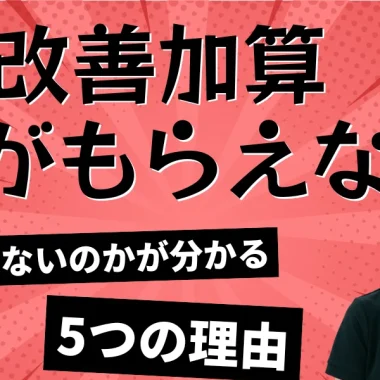








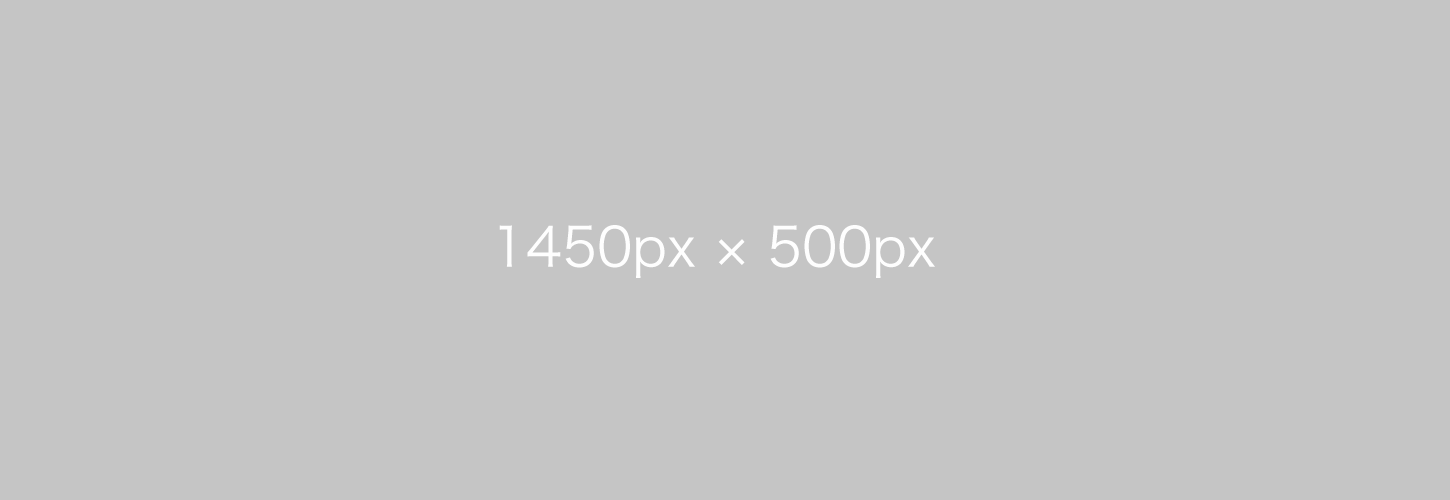
コメント