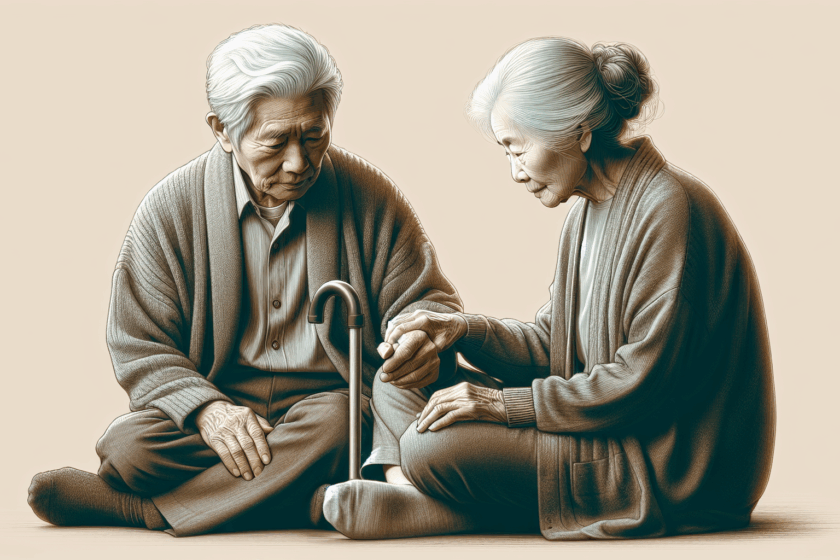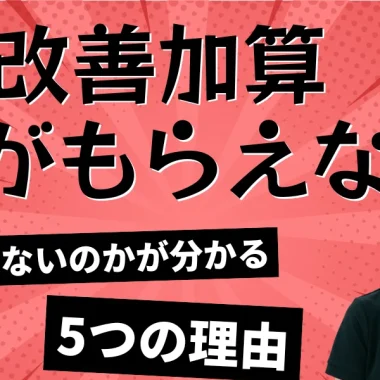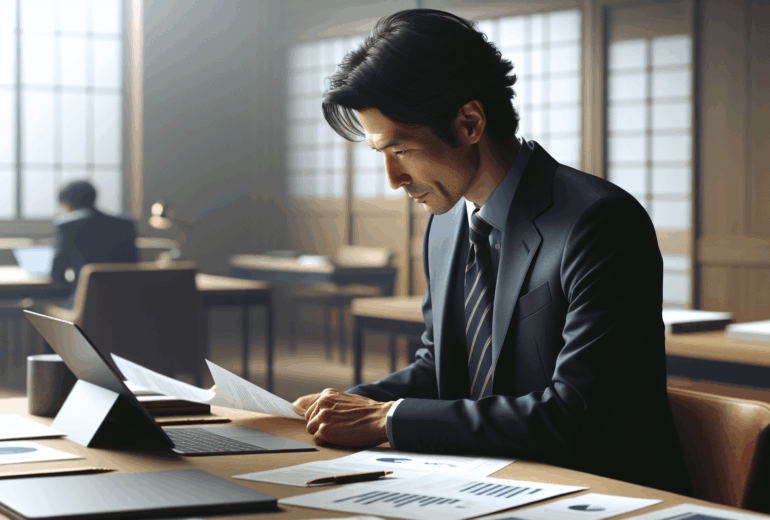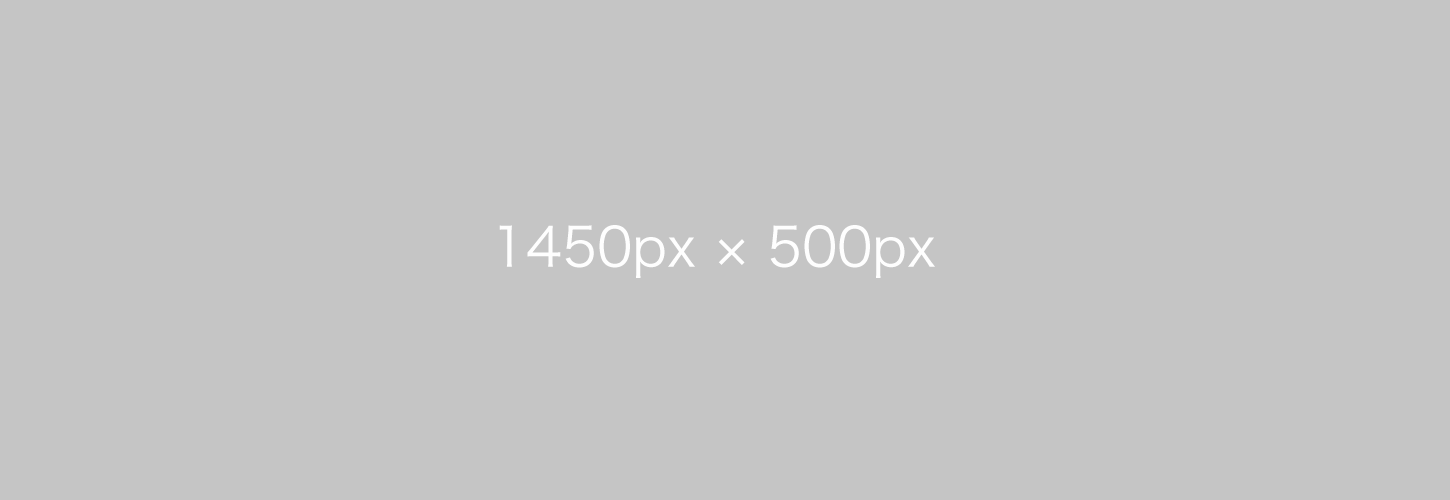「自分も70代なのに、同じ家で暮らす90代の母の介護が続いている。いつまで体がもつのだろう」――久留米市で老々介護を続ける家族から、こうした声が増えています。
久留米市の人口は約30万人、そのうち65歳以上は約8万4千人で、高齢化率は約28%です。(caravanmate.com) 2040年には34%、2050年には37%を超える見通しが示され、高齢者どうしの介護がさらに増えると予測されています。(GDFreak)
久留米市御井旗崎にある住宅型有料老人ホーム「有料老人ホームはたさき」にも、老々介護に限界を感じた家族から「入所のタイミング」や「ショートステイの使い方」に関する相談が日常的に寄せられます。地域の現場では、数字の変化がそのまま家庭の負担として表面化している状況です。
この記事では、
- 久留米市における老々介護の実態と高齢化の数字
- 家族に起こりやすいリスクと具体的な困りごと
- 久留米市で使える介護サービスや老人ホームの選び方
- 家族・介護職・地域が今から取れる行動計画
を、「原因 → 結果 → 行動」の流れで整理します。被介護者を持つ家族、高齢者施設で働く方、介護にかかわるあらゆる方が、自分のケースに置き換えて動きやすくなることを目指した内容です。
久留米市で増える老々介護と高齢化の数字
久留米市の高齢化率は約28〜29%で、全国平均と同水準かそれ以上の水準に達しています。(caravanmate.com) 要介護・要支援認定者は1万5千人台にのぼり、老々介護の家庭も着実に増えています。(GDFreak) この章では、日本全体のデータと久留米市の数字を重ねながら、老々介護が増える流れを整理し、今後20〜30年を見すえた考え方をまとめます。
老々介護とは何か―日本と久留米の数字でつかむ現状
老々介護とは、65歳以上の人が同じく65歳以上の家族(配偶者や親など)を介護する状態を指します。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、「要介護者」と「同居の主な介護者」がいずれも65歳以上の世帯は63.5%まで増え、20年前の約1.5倍に達しました。(厚生労働省) この数字は、高齢者どうしの介護が例外ではなく、むしろ一般的な形になっていることを意味します。
久留米市も同じ流れの中にあります。市内の高齢化率は約28%で、今後も上昇が続くことが推計されています。(caravanmate.com) 高齢者世帯が増え、子ども世代が福岡市や首都圏へ転出することで、夫婦のみ・高齢の親子のみの世帯が増えました。その結果、介護が必要になったときに担い手が同じ世帯の高齢者しかいないケースが目立ちます。
こうした背景を踏まえると、「老々介護になる前に準備する」視点が欠かせません。具体的には、
- 70代に入った時点で、地域包括支援センターに一度相談し、将来の介護について情報を集める
- 家族で「介護が必要になったらどうするか」を、年1回は話し合う
- かかりつけ医に、介護が必要になった場合の医療との連携イメージを質問しておく
といった動きを早めに取ることで、突然の老々介護で追い込まれるリスクを減らせます。
久留米市の人口構造と要介護認定者数から見えること
久留米市では、人口約30万人のうち約8万4千人が65歳以上で、高齢化率は約28%です。(caravanmate.com) 要介護・要支援認定者は約1万5千人台で、推計値より9%ほど多い状況となっています。(GDFreak) つまり、高齢者の中でも、介護サービスを必要とする人が想定以上に増えている状態です。
高齢化率だけでなく、次のような数字も押さえておくと、久留米市の介護の全体像がつかみやすくなります。
| 指標 | 数字の目安 | 意味するところ |
|---|---|---|
| 高齢化率 | 約28〜29% | 3人に1人に近い割合で高齢者が暮らしている |
| 要支援・要介護認定者数 | 約1万5千人台 | 介護保険サービスの利用ニーズが高い |
| 今後の高齢化率(2040→2050) | 34% → 37%超へ上昇見込み(GDFreak) | 老々介護の増加が長期的に続く可能性が高い |
これらの数字から分かるのは、「今だけでなく、10〜20年先まで老々介護が続く地域になる」という現実です。
その結果、家族だけで介護を背負う形では、体力・経済・精神のどれかが先に行き詰まりやすくなります。そこで、家庭内だけに介護を閉じ込めず、早い段階から地域包括支援センター・ケアマネジャー・老人ホームの相談窓口など、外部の専門家と関係を作っておく行動が求められます。
御井旗崎エリアと老人ホームの現場から見える老々介護
久留米市御井旗崎は、住宅街と介護施設が混在するエリアで、地域の中に高齢者の生活と介護サービスが入り込んでいる地域です。住宅型有料老人ホーム「有料老人ホームはたさき」やデイサービス事業所などがあり、老々介護に悩む家族からの相談を日常的に受けています。
現場の感覚では、次のような変化が生まれています。
- 同居している子ども世代が60代後半、親が90代の「子どもも高齢」のケースが増えた
- 夫婦2人暮らしで、どちらかが認知症を発症し、もう一人が介護に追われる世帯が目立つ
- 介護者自身に心臓病や糖尿病などの持病があり、急な入院で在宅介護が続けられなくなる
原因は、平均寿命の延びと家族構成の変化です。結果として、老人ホームやショートステイを「急に探す」相談が増え、空きベッドをめぐる調整に時間がかかる場面が出てきます。
こうした事態を避けるために、
- 75歳を過ぎたら、近隣の老人ホームやグループホームを1〜2か所、見学しておく
- 要介護認定を受けたタイミングで、ショートステイやデイサービスの利用も同時に検討する
- 家族が倒れたときに「どの施設にお願いするか」を、ケアマネジャーと事前に共有しておく
といった行動を取ることで、「限界になってから探す」状態から一歩抜け出しやすくなります。
老々介護が家族にもたらすリスクと具体的な困りごと
老々介護では、介護する側も高齢であるため、心身への負担が蓄積しやすくなります。久留米市では、介護者の6割前後が60歳以上という調査結果も報告されており、介護者自身の健康が大きなテーマになっています。(earthsupport.net) この章では、老々介護で起こりやすいリスクを整理し、その結果として起こりうる事態、そのうえで取るべき行動を具体的に示します。
共倒れ・転倒・急病のリスクを減らす視点
原因としてまず挙げられるのが、「介護者も要介護者も体力が落ちている」という事実です。70代・80代の介護者が、同じ年齢層の配偶者や親を抱き起こしたり、入浴介助を行ったりすれば、腰や膝への負荷が蓄積します。夜間のトイレ介助が重なると睡眠不足も重なり、ふらつきや転倒のリスクが高まります。
結果として、次のような事態が起こりえます。
- 介護中の転倒で介護者が骨折し、二人とも自宅で生活できなくなる
- 介護者の持病(心疾患・糖尿病など)が悪化し、救急搬送が必要になる
- 介護者が体調不良を我慢した結果、要介護者の通院や服薬が滞る
こうした事態を防ぐ行動として、具体的にすすめたいのは次の3つです。
- 1日の介護内容を書き出し、「力仕事」と「見守り」に分ける
- 力仕事が多い部分を、訪問介護や福祉用具(ベッド・リフトなど)で置き換えられないか、ケアマネジャーに相談する
- 介護者自身の通院日を、デイサービスやショートステイと組み合わせて確保する
原因(体力低下)を前提に、結果(共倒れ)を避けるには、「どこまで自分でやるか」「どこからサービスに任せるか」を言語化することが第一歩になります。
孤立・うつ・虐待を招く心の疲れ
老々介護では、身体の疲れだけでなく「相談できない」「誰にも見てもらえない」という孤立感が心の疲れを深めます。高齢の夫や妻が一人で介護を抱えると、「迷惑をかけたくない」「家のことだから外には言いにくい」という気持ちから、支援を断ってしまう場面が少なくありません。
結果として、
- 介護者がうつ状態になり、食欲低下や不眠に悩まされる
- イライラがたまり、きつい言葉や暴力的な関わり方になってしまう
- 介護者自身が「もう限界だ」と感じたときに、相談窓口が思い浮かばず追い詰められる
といった危険につながります。全国的にも、高齢者虐待の背景に介護者の疲労と孤立があるケースが多く報告されています。(老施協デジタル)
久留米市で心の疲れを軽くする行動としては、
- 地域包括支援センターに電話を入れ、「愚痴を聞いてほしい」と正直に伝える
- 久留米市社会福祉協議会やNPOが開催する「介護者カフェ」に月1回参加してみる(earthsupport.net)
- 民生委員に自宅訪問を依頼し、見守りと会話の機会を増やす
といった小さな一歩が有効です。「助けてと言うこと」自体が行動であり、老々介護の行き詰まりを緩める起点になります。
認知症が重なる「認認介護」の危うさ
原因がさらに複雑になるのが、介護者・要介護者の双方に認知症の症状がある「認認介護」です。久留米市内でも、80代の夫婦が共に物忘れや判断力の低下を抱えながら生活し、そのうち片方が要介護認定を受けるケースが出ています。
認知機能が落ちた状態で介護を続けると、
- 服薬の飲み忘れ・二重飲みが増え、体調悪化や転倒につながる
- ガス栓や電気ポットの消し忘れが重なり、火災や事故のリスクが高まる
- 金銭管理ができず、公共料金の滞納や詐欺被害が起こる
といった結果を招きます。数字で見ると、2022年の調査では「要介護者」と「同居の主な介護者」の組み合わせがともに75歳以上の割合は35.7%まで上昇しており、認認介護のリスク層が全国的に増えています。(厚生労働省)
認認介護が疑われる場合、早期の行動が欠かせません。
- かかりつけ医に「家族も物忘れが増えている」と伝え、双方の認知症チェックを受ける
- 地域包括支援センターに、「認知症の家族が二人暮らしで不安」と相談を入れる
- グループホームや認知症対応型デイサービスを、早めに見学・体験利用する
久留米市には、認知症サポーターが約4万人登録されており、認知症の人と家族を支える活動が広がっています。(久留米市公式サイト) このネットワークを活かすことで、認認介護を家庭内だけの問題にせず、地域で分け合う形に近づけられます。
久留米市で使える介護サービス・老人ホーム・相談窓口
老々介護のリスクを減らすには、在宅サービスと老人ホームなどの施設サービスを「早めに知り、少しずつ利用する」ことが欠かせません。久留米市には、地域包括支援センター11か所を基盤に、在宅介護から施設入所までつながる仕組みが整えられています。(久留米市公式サイト) この章では、相談の入口からサービス選び、老人ホームのチェックポイントまで、行動のステップを整理します。
地域包括支援センターに相談するときの手順
地域包括支援センターは、高齢者と家族の総合相談窓口です。久留米市では、市内を11ブロックに分け、それぞれにセンターが配置されています。(久留米市公式サイト) 保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士がチームで対応し、介護・医療・福祉・権利擁護など、幅広い相談を受け付けています。
利用の流れを、原因→結果→行動で整理すると次の通りです。
- 原因:自宅での介護が続き、家族が「体力的にも精神的にも限界に近い」と感じ始める
- 結果:情報不足のまま我慢を続けると、共倒れや虐待、介護離職などのリスクが高まる
- 行動:限界を迎える前に、地域包括支援センターに電話または来所で相談する
相談時には、次の情報をメモして持参すると、話が進みやすくなります。
- 要介護認定の有無と、要介護度
- 1日の過ごし方(起床時間、食事、トイレ、入浴、就寝時間など)
- 家族の人数と、それぞれの仕事・健康状態
センターでは、
- 現状の聞き取り
- 必要であれば要介護認定の申請支援
- 居宅介護支援事業所や老人ホームの紹介
といった流れで支援してくれます。相談料は無料で、平日8時30分〜17時15分の間で利用できます。(久留米市公式サイト) 「どこに相談したらよいか分からない」と感じた時点で一度連絡を入れることが、問題の早期発見につながります。
在宅サービス(訪問介護・デイ・ショートステイ)の組み合わせ方
在宅介護を続けながら、家族の負担を抑えるには、介護サービスを組み合わせる発想が欠かせません。久留米市でも、訪問介護・訪問看護・デイサービス・ショートステイなど、多くのサービス事業所が運営されています。(久留米市公式サイト)
代表的な組み合わせ例を、表で整理します。
| 家族の課題 | サービス | 利用頻度の例 | 期待できる変化 |
|---|---|---|---|
| 毎日の入浴介助が負担 | デイサービス | 週2回通所 | 入浴を任せて、家族は腰への負担が下がる |
| 夜間の見守りで眠れない | ショートステイ | 月1回・2〜3泊 | まとまった睡眠を取り、体調を回復しやすくなる |
| 買い物や掃除に時間が取られている | 訪問介護(生活援助) | 週1〜2回・1時間 | 家事を任せて、家族が休息や通院の時間を確保 |
原因として「家族がすべての介護と家事を抱え込む」状態があると、結果として介護疲れと健康悪化が重なります。行動として、ケアマネジャーと次のような方針を話し合うことが大切です。
- 「入浴だけは外部に任せる」「夜間は月1回施設にお願いする」など、任せる範囲を決める
- 介護者の通院日・買い物日を決め、その日に合わせてサービスを組み込む
- 利用開始後1〜3か月ごとに、家族の負担感を確認し、プランを見直す
こうした具体的な設計を行うことで、「サービスを使っても結局疲れが取れない」という状況を避けやすくなります。
老人ホーム・有料老人ホームを選ぶときのチェックポイント
在宅介護だけでは支えきれない場合や、老々介護で共倒れのリスクが高い場合、老人ホームへの入所や短期利用を選択肢に入れることが現実的です。久留米市には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、施設系サービスが多数あります。(earthsupport.net)
選ぶ際の基準を、「原因→結果→行動」で整理してみます。
- 原因:自宅での介護が続き、夜間も含めた見守りが必要になった
- 結果:家族の睡眠不足・持病の悪化・事故のリスクが増える
- 行動:24時間体制で見守りが行われる老人ホームの情報を集め、2〜3施設を見学する
見学時に確認したいポイントは、次の通りです。
- 医療連携
- 近隣の病院との連携体制、夜間の緊急時の流れ
- 生活の様子
- 食事・入浴・レクリエーションの雰囲気、入居者同士の関係性
- 家族との関わり方
- 面会のしやすさ、オンライン面会の有無、看取りの方針
例えば、久留米市御井旗崎にある「有料老人ホームはたさき」のように、デイサービスや訪問介護と連携し、在宅から施設まで一体的に支える事業所もあります。こうした拠点を持つ法人に相談し、「在宅で続ける期間」と「入所を検討するタイミング」の両方について、複数年の視点で計画を立てておくと、急な判断に追われにくくなります。
介護者・施設・地域が今から取れる行動計画
老々介護は、家族だけで抱えると限界が来やすいテーマですが、久留米市には行政・医療・介護・地域住民をつなぐ仕組みが整いつつあります。(社会福祉法人 久留米市社会福祉協議会) この章では、家族・老人ホームやデイサービスなどの事業所・地域の3つの立場から、具体的な行動計画を整理します。
家族が1か月以内に進めたい3つのステップ
まずは、被介護者を持つ家族が「この1か月でできること」に焦点を当てます。原因は、介護の負担が見えにくいまま日々が過ぎ、気づいたときには限界を超えていることです。結果として、共倒れや介護離職につながります。
1か月以内に取り組みたいステップは次の3つです。
- 介護の内容を書き出す
- 1日の流れを30分単位で記録し、「誰が・何を・どれくらい」行っているかを見える化する。
- 相談先の電話番号リストを作る
- 地域包括支援センター、かかりつけ医、ケアマネジャー、近隣の老人ホームなど、5〜10件の連絡先を手帳やスマホにまとめる。
- レスパイト(休息)の日をカレンダーに入れる
- デイサービスやショートステイを利用し、「この日は介護を人に任せる日」と決める。月1回から始めるだけでも違いが出る。
この3つを進めることで、「感覚的な疲れ」を「見える化された課題」に変えやすくなります。そのうえで、地域包括支援センターやケアマネジャーと一緒に、3か月・半年単位の介護計画を作成していくと、長期戦に備えた準備になります。
老人ホームや通所施設の職員ができる地域連携
老人ホームやデイサービスの職員にとっても、老々介護は身近なテーマです。原因として、施設利用者の家族が高齢化し、「入所中だけでなく、外泊時や退所後の生活も老々介護になる」ケースが増えています。
結果として、
- 退所した後に介護が続かず、短期間で再入所の相談が入る
- 家族が介護疲れで通所を休みがちになり、在宅生活が不安定になる
- 施設側も、家族の状況を把握しきれず支援が後手に回る
といった事態が起こりやすくなります。
職員側の行動としては、次のような取り組みが考えられます。
- 入所・通所時のアセスメントで、「主な介護者の年齢・持病・仕事状況」を必ず確認する
- 老々介護が想定される家庭には、早い段階で地域包括支援センターや民生委員と情報を共有する(本人・家族の同意を得たうえで)
- 面会や送迎の際に、介護者の表情や疲労度を定期的にチェックし、変化があればケアマネジャーに共有する
久留米市内には、認知症サポーター約4万人と、キャラバン・メイト約400人が登録されており、地域で認知症や介護を支える土台があります。(久留米市公式サイト) 施設職員がこのネットワークと積極的につながることで、老々介護家庭への支援が一段広がります。
久留米ならではのネットワーク(認知症サポーター・民生委員・NPO)の活かし方
久留米市では、行政だけでなく、社会福祉協議会・民生委員・NPO法人など、多くの主体が介護と暮らしを支えています。(社会福祉法人 久留米市社会福祉協議会)
原因として、高齢化の進行と単身高齢者の増加があります。結果として、地域での見守りや声かけがないと、孤立死や認知症の行方不明といったリスクが高まります。
そこで、地域のネットワークを活かす行動が重要になります。
- 認知症サポーター養成講座に参加し、「オレンジリング」を身につけて、身近な高齢者への声かけを増やす
- 民生委員・主任児童委員の活動内容を知り、必要なときに相談しやすい関係をつくる
- 久留米市社会福祉協議会が主催する小地域ネットワーク活動やサロンに顔を出し、介護者・高齢者との接点を増やす(社会福祉法人 久留米市社会福祉協議会)
久留米市では、認知症サポーター約4万人という数字そのものが、「地域で支え合う土台」の広がりを示しています。(久留米市公式サイト) 老々介護を家族だけの問題にしないためにも、こうしたネットワークに一歩踏み出して参加することが、地域全体の介護力を高める行動につながります。
おわりに:久留米で老々介護と向き合うために
久留米市の高齢化率は約28〜29%、要支援・要介護認定者は1万5千人台に達し、今後も増加が見込まれています。(caravanmate.com) 老々介護は、もはや一部の家庭だけの話ではなく、多くの家族が直面しうる現実です。
原因は、平均寿命の延びと家族構成の変化、高齢者世帯の増加です。結果として、高齢者が高齢者を支える構図が普通になり、共倒れや孤立のリスクが高まっています。
この現実の中で取れる行動は、決して特別なものではありません。
- 1日の介護内容を見える化し、負担の「量」と「質」を把握する
- 地域包括支援センターやケアマネジャーに早めに相談し、在宅サービスやレスパイトを組み合わせる
- 老人ホームや有料老人ホームを「最後の選択肢」ではなく、「暮らしを守る一つの手段」として情報収集しておく
- 認知症サポーター講座や介護者カフェに参加し、地域の仲間とつながる
久留米市御井旗崎の「有料老人ホームはたさき」を含め、市内には多くの介護事業所や老人ホームがあります。現場の専門職や地域のネットワークを味方につければ、家族だけで抱え込まない介護の形を描けます。
「今のままで続けてよいのか」と不安を抱えたときこそ、行動を変えるチャンスです。まずはお住まいの地域の地域包括支援センターに電話を入れ、「久留米で介護を続けるうえで、どんな選択肢があるか教えてほしい」と一言伝えてみてください。そこから、老々介護を少しでも軽くする次の一歩が見えてきます。